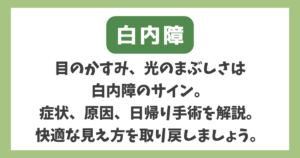白内障は加齢とともに多くの人が直面する目の病気で、日常生活に支障をきたすこともあるため手術をすすめられることも少なくありません。
しかし、手術と言われると「費用はどのくらい?」「保険は使える?」「高額になったらどうしよう」と不安になる方もいるかもしれません。
この記事では、白内障手術の費用の目安をはじめ、費用を抑えるための制度や方法、患者さんからよく寄せられる疑問についてわかりやすく解説します。
これから手術を検討されている方や、ご家族のために情報を集めている方は、ぜひ参考にしてください。
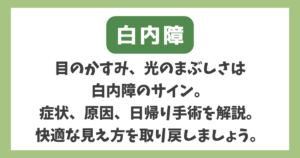
白内障の手術費用の目安は?

白内障手術は、手術方法や挿入する眼内レンズの種類によって費用が大きく異なります。
ここでは、手術の方法や眼内レンズについて詳しく解説し、それぞれの費用目安を紹介します。
白内障手術の種類
白内障の手術は超音波で濁った水晶体を破砕し取り出す超音波乳化吸引術と、レーザーで切開を行うレーザー白内障手術があります。
一般的に行われるのは超音波乳化吸引術で、保険が適用されます。
一方、レーザー白内障手術は眼科によって費用に幅がある自由診療です。
眼内レンズの種類は、単焦点レンズ(保険適用)、多焦点レンズ(手術費用が保険適用+レンズ代は自費で賄う選定診療)で、それぞれ以下のような特徴があります。
| 単焦点眼内レンズ(保険適用) | 多焦点眼内レンズ(選定療養) | |
|---|---|---|
| 長所 | ・コントラストがはっきりしている ・費用が抑えられる | ・遠距離、中距離、近距離の3点にピントが合う ・眼鏡をかける必要が少ない ・一部費用は保険適用 |
| 短所 | ピントを合わせた箇所以外を見る場合には 眼鏡が必要になる | ・暗いところで見えにくい ・まぶしさを感じやすい ・多焦点眼内レンズ代が高額 |
選定療養として認められていない多焦点レンズ(未承認レンズ)を使用する場合は、手術費用も含めて全額自費となります。
一般的な保険適用手術の費用目安
一般的に行われる超音波乳化吸引術と単焦点レンズの組合せは保険適用ですが、負担割合によって差があります。
超音波乳化吸引術と単焦点レンズの場合、それぞれの負担割合の費用目安(片目)は以下の通りです。
| 3割負担の方 | 5~6 万円 |
|---|---|
| 2割負担の方 | 3~4 万円 |
| 1割負担の方 | 約 2 万円 |
多焦点レンズを選ぶ場合は一部費用が保険適用となり、レンズ代の追加費用がかかる選定医療となります。
多焦点レンズ代はレンズの種類と乱視の有無で費用が変わり、乱視なしレンズは23~31万円程度、乱視ありレンズは26~37万円程度が一般的です。
レンズ費用は自己負担となりますが、それ以外の手術代、診察代、検査代、薬代は保険診療で受けられます。
入院手術の費用目安
白内障手術は、主に日帰り手術で行われますが、高血圧や糖尿病などの持病がある方は入院が必要になる場合があります。
入院手術の一般的な費用目安は以下の通りです(別途差額ベッド代、食事代などがかかります)。
| 3割負担の方 | 6~7 万円 |
|---|---|
| 2割負担の方 | 4~5 万円 |
| 1割負担の方 | 2~3 万円 |
差額ベッド代や食事代は病院によって異なるため、入院する際は事前に確認しましょう。
片目手術と両目手術の費用
両目を手術する場合には、費用は一般的に片目の2倍となります。
白内障の手術は同時に両目を行うことはほとんどなく、片目手術を行った1~2週間後にもう一方の目を手術するケースが多いです。
これは、手術後の細菌感染による眼内炎のリスクを防ぐためと、術後の見え方の違和感による生活への影響を少なくするためです。
自由診療の白内障手術の費用
厚生労働省認可外のレンズを使用する場合は、健康保険の適用がないため全額自己負担となります。
日帰り超音波手術・片目で40~60万円程度、レーザー白内障手術では片目50~70万円程度が費用の目安です。
使用するレンズによって費用に大きく差が出るため、さらに費用がかかることもあります。
眼内レンズを選ぶ際は、メリット・デメリットをしっかり聞いて納得したうえで、自分に合ったものを選びましょう。
白内障の費用負担を減らす方法

白内障の費用は、手術を伴うため高額になる可能性がありますが、制度や保険を活用することで負担の軽減が可能です。
ここでは、費用負担を軽減する方法を5つ紹介します。
自己負担額の確認
年齢や所得に応じて、保険診療の自己負担額は1割、2割、3割に分類されます。
負担割合に応じて費用が変わるため、自身の負担割合を知っておくことが重要です。
負担割合の分類の詳細は以下の通りです。
| 年齢 | 自己負担割合 | ||
|---|---|---|---|
| 健康保険 国民健康保険 | 未就学児 | 2 割 | |
| 小学生~69 歳 | 3 割 | ||
| 70~74 歳 | 2 割 | ||
| 3割(現役並み所得者) | |||
| 後期高齢者 医療制度 | 75 歳以上 | 一般所得者 | 1 割 |
| 一定以上の所得者 | 2 割 | ||
| 現役並み所得者 | 3 割 | ||
現役並み所得者とは、世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合は年収383万円以上、2人以上いる場合は合計年収520万円以上を指します。
この場合の年収とは、年金収入にその他の合計所得金額を足したものです。
また、図中の『一定以上の所得者』とは、年収が200万円以上383万円未満の場合(後期高齢者が世帯内に1人)です。
後期高齢者が世帯内に2人以上の場合は、年金収入とその他の合計所得金額が320万~520万円の場合は医療費が2割負担となります。
高額医療費の還付
日本では、医療費の負担を軽減するため、高額療養費制度があります。
高額療養費制度は、1か月(1日~月末まで)の医療費の自己負担額が、所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が後から払い戻される制度です。
また、高額療養費制度は以下のような仕組みでさらに負担が軽減できます。
- 世帯合算:同じ健康保険に加入している同一世帯の医療費は合算できる
- 多回数該当:直近12か月ですでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合にはその月の負担の上限がさらに引き下がる
払い戻しは、加入している健康保険に支給申請書を送ることで受けられるため、申請の方法を確認しておきましょう。
限度額適用認定証
本来は、上限額を超えた医療費の払い戻しには3か月程度かかりますが、限度額適用認定証を医療機関にあらかじめ見せることで、受付で上限額を支払うだけですみます。
以前は限度額適用認定証を事前に申請し準備しなければいけませんでしたが、マイナンバーカード(マイナ保険証機能)を利用すると限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。
70歳未満の自己負担限度額
高額療養費の毎月の上限額は、加入者の年齢や所得水準によって分けられます。
70歳未満の加入者のひと月の自己負担上限額は以下の通りです。
| 適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬83万円以上 国保:所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬53~79万円 国保:所得600~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 健保:標準報酬28万~50万円 国保:所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ~年収約370万円 健保:標準報酬26万円以下 国保:所得210万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳未満の場合は、ひとつの医療機関で上限を超えない場合でも、他の医療機関で21,000円以上の自己負担分があれば合算できます。
同月であればいくつかの医療機関の合算額が上限を超えれば高額療養費の支給対象になります。
70歳以上の自己負担限度額
70歳以上の自己負担限度額は、70歳未満よりも細かく区分が分かれるため、注意が必要です。
| 適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
| 年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | |
| 年収約370万円~約770万円 標報28万円以上 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
| 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 | 18,000円(年144,000円) | 57,600円 |
| Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | |
70歳以上では、他の医療機関の医療費は条件なく合算することができます。
同じ月に両目とも手術する
白内障手術は、眼内炎のリスクを避けるため、また、術後の見え方の違和感による生活への支障が懸念されるため、片目ずつの手術を行うのが一般的です。
片目を手術した1~2週間後にもう一方の目の手術になる場合が多いですが、月ごとの医療費の上限を考えて行うのがおすすめです。
手術費用の総額が自己負担限度額を超える場合には、同月内に両目とも手術を受けるほうが費用を抑えられます。
手術の日程に関しては、医療費も加味したうえで医師と相談してタイミングを決めましょう。
加入している医療保険
個人で生命保険に加入している方は、白内障の手術を受けた際に手術給付金が貰える可能性があります。
また、保険の内容によっては、選定療養(多焦点レンズなど)や自由診療といった保険適用でない手術でも、一部の費用に対して給付金が出る場合があります。
給付金を受け取れるかどうかは、保険の種類や内容によって異なるため、加入している生命保険会社に確認してみましょう。
多焦点レンズは医療費控除の対象
医療費控除とは、前年の1月1日から12月31日までの間に、本人や同一生計の家族が医療費を支払った場合、一定の金額を所得から差し引く制度です。
多焦点眼内レンズは保険は適用されませんが、医療費控除の対象になります。
選定療養(多焦点レンズの追加費用)を含んだ白内障手術の自己負担額は、医療費控除の対象です。
自由診療では、支払った金額すべてが医療費控除の対象になります。
白内障手術のよくある疑問

白内障手術を検討していると、さまざまな疑問や不安が出てくる方もいるかもしれません。
ここでは、患者さんが悩みやすい疑問をピックアップし、回答していきます。
手術を前に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。
- レンズはどう選べばいいですか?
-
眼内レンズは、水晶体のようにすべてのものにピントを合わせることはできません。
そのため、普段自分が生活の中で一番見ている距離、見たい距離を考えることが大切です。
見たい距離が裸眼で明るく見える眼内レンズが適したレンズです。
生活の中の作業で一番大切にしているものをもとに、医師と相談して自分に合ったレンズを選びましょう。
- 70歳以上になってから手術を受けるべきですか?
-
健康保険、高額療養費制度、限度額適用認定証などは、70歳を境目に自己負担限度額が変わります。
そのため、白内障手術を行う際も急いで手術を行う理由がない場合は、費用を軽減することができます。
ただし、白内障によって日常生活や仕事などに支障をきたしている場合や過度に進行した白内障の場合は、70歳まで待たずに早めの手術を行うことが大切です。
手術のタイミングについては医師と話し合い、70歳まで待てるかどうか聞くのもおすすめです。
- 術後の定期検査は保険適用ですか?
-
術前・術後の検査は保険適用になります。
選定療養である多焦点レンズを選んだ場合でも、検査は保険適用となります。
自由診療の場合、術後の検査も自由診療になるのが一般的です。
- 手術に付き添いは必要ですか?
-
白内障手術当日は、必ず付き添いが必要というわけではありません。
しかし、手術後は眼帯をするため片目が見えづらくなり、視野が狭くなるため、高齢の方や身体に不安のある方は付き添いがあると安心です。
また、手術後は車の運転ができないため、送迎のサポートをすることをおすすめします。
手術を受ける方は不安が大きい場合もあり、付き添いの方がいると安心感につながります。
まとめ
白内障手術は、手術内容と眼内レンズの種類によって、保険診療、選定療養、自由診療のどれになるかが変わります。
費用も大幅に変わってくるため、事前に知っておくことで、術式やレンズを選ぶ際の指針となるかもしれません。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、日帰り白内障手術を行っています。
単焦点レンズはもちろん、多焦点レンズも選定療養の範囲で種類を取り揃えています。
白内障手術の費用についてわからないことや不安なことはぜひご質問ください。