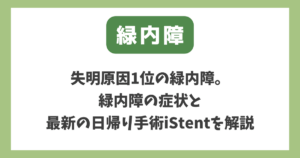緑内障と診断されてから失明まで、どれくらいの期間なのかを不安に感じている方は少なくありません。
目が見えなくなるかもと心配で、目の違和感に敏感になりすぎて生活に支障が出てしまう方もいます。
しかし、緑内障になっても必ずしも失明するわけではありません。
適切な治療をきちんとしていれば、生涯視力を維持したまま過ごすことも可能です。
この記事では、緑内障と失明、白内障との関係、眼科検診の大切さなどについて、詳しく解説します。
失明が不安な方、緑内障について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
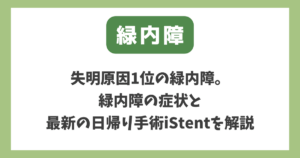
緑内障の失明までの期間は年齢では変わらない

緑内障の失明までの期間は、年齢による要素だけではほとんど差はありません。
後述しますが、他の複数の要素が重なり合って、発症率や進行度に関連してきます。
一般的に60代(高齢)になると進行が早く失明する確率が高いと言われるのは、年齢を重ねると目の組織が老化で弱くなり、視神経がダメージを受けやすくなるためだと考えられています。
しかし、緑内障を早期発見して、すぐに治療を開始すれば、高齢であっても進行を抑制することは可能です。
緑内障は失明原因第1位
2019年に行われた調査によると、緑内障は日本の失明(視覚障害)の原因第1位で、全体の40.7%を占めているとわかりました。
第2位は網膜色素変性症(13.0%)、第3位は糖尿病網膜症(10.2%)です。
(参照:岡山大学)
2018年に視覚障害の認定基準改定がされた影響もありますが、緑内障における失明者が2015年は28.6%であり、4年間で10%以上増加しています。
ただし、失明する原因としては約40%ですが、日本の緑内障患者数は465万人以上と推定されていて、そのなかでも失明する割合としてはさほど高くありません。
患者数が多い分、失明の原因になりやすいと考えられています。
40代から発症率が上がる
緑内障は40代以上で20人に1人(5%)、60代で6.3%、70代で10.5%の有病率と調査の結果が出ています。
(参照:「日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査(通称:多治見スタディ)報告」日本緑内障学会)
40歳以上になると緑内障の発症率が上がり、診断を受けていなくても緑内障を患っている方も増えていると考えられます。
しかし、若年層でも発症する可能性はあり、眼圧が正常範囲内(10mmHg~21mmHg)でも発症する正常眼圧緑内障は、20~30代の方も多いです。
加齢だけが原因ではなく、遺伝や強い近視など複数の要素が重なり緑内障になることもあります。
早期発見・早期治療が重要
緑内障は早期発見・早期治療が重要な病気です。
緑内障になると、眼圧上昇や他の要因により視神経が障害されて、映像情報が目から脳へ上手く伝達されなくなります。
ダメージを受けた視神経が担っていた部分の視界が欠けていくのが、緑内障で現れる主な症状です。
機能を失った視神経は元に戻すことが困難で、失った視力や視野は回復しません。
そのため、緑内障では症状を今以上に進行させないことを目的とする治療が行われます。
早期発見すれば、その分だけ無事な視神経を守ることができ、視力や視野を保てる可能性が高まります。
緑内障は初期にはほとんど自覚症状がなく、早期発見するためには定期的な眼科検診を受けることが欠かせません。
適切な治療を継続する
緑内障の治療は完治を目指すものではなく、今の視力を維持するために継続して行うものです。
治療方法は点眼治療やレーザー治療、手術などがありますが、それぞれの症状や状況に合わせて医師の指示に従い行います。
点眼治療は自宅で毎日点眼薬をさすことになり、手間を感じて途中で治療をやめてしまう方も多く、問題になっています。
また、視力が改善するわけではないため、治療している実感が得にくく、消極的になってしまうかもしれません。
しかし、点眼治療で眼圧をコントロールするのは非常に重要な緑内障の治療です。
適切な治療を継続して行えば、一生見える目を守ることにもつながります。
緑内障の進行速度に影響する要素

緑内障の進行度は、加齢だけでなくさまざまな要素が影響します。
緑内障の種類や健康状態、生活習慣などにより、進行速度が変わる可能性があるのです。
緑内障は以下のような分類があります。
| 名称 | IPL脱毛 |
|---|---|
| 原発開放隅角緑内障 | 隅角は開放されているが、その先の異常により房水の排出がスムーズにいかなくなる 正常眼圧緑内障を含む |
| 原発閉塞隅角緑内障 | 隅角が閉じる、または狭くなって房水が眼球内に溜まり視神経を圧迫する 急性緑内障発作が起こる可能性がある |
| 続発緑内障 | 原因となる他の目の病気や全身の疾患がわかっている 開放型と閉塞型がある |
| 小児緑内障 | 生まれつきの目の異常や成長とともに症状が現れ、一部は遺伝的要素もある |
開放型は症状の進行が遅く、数年~数十年かけてゆっくり進んでいき、初期よりも後期の方が進行速度が速まるとされています。
閉塞型でも慢性の場合は開放型と同様ですが、急性の場合は後述する急性緑内障発作が起きる可能性があるため注意が必要です。
また、強い近視で眼球の変形が起こっていたり、糖尿病や睡眠時無呼吸症候群、高血圧・低血圧などの疾患があったりすると、進行度にも影響します。
他にも緑内障の進行速度に影響があると考えられる生活習慣は、喫煙習慣や過度なアルコール摂取、下を向く姿勢が長いなど、目への負担が多いものです。
緑内障で失明する可能性がある?急性緑内障発作について

緑内障の中でも、閉塞隅角緑内障で起こりやすい急性緑内障発作には緊急の対応をしなければいけません。
ここでは、失明する可能性がある急性緑内障発作について、詳しく解説します。
急性緑内障発作とは
急性緑内障発作は、閉塞隅角緑内障で隅角が突然閉じることによって起こります。
急激に眼圧が上がり、視神経が一気に大きなダメージを負う可能性があります。
放置すると一晩~数日で視力を失うこともあるため、一刻も早く眼圧を下げる処置が必要です。
急性緑内障発作の症状
急性緑内障発作では、以下のような症状が現れます。
- 激しい目の痛み
- 目のかすみ
- 充血
- 急激な視力低下
- 激しい頭痛
- 吐き気
- 嘔吐 など
突然これらの症状が現れた場合は、急性緑内障発作の可能性があるため、すぐに眼科を受診しましょう。
夜間や救急では眼科の専門医がいないこともあり、脳の疾患と間違われて緑内障を見逃してしまうと処置が遅れてしまいます。
急性緑内障発作は目の痛みを伴うため、必ず目についての症状を医師に伝えるようにしましょう。
急性緑内障発作の治療
急性緑内障発作では、急激に上がった眼圧を下げるため、即効性の内服薬や点滴、点眼薬を使った処置が行われます。
これらの治療で眼圧が下がりきらなかったり、今後の再発を予防する必要があったりする場合は、レーザー治療や手術を行うこともあります。
緑内障と白内障の関係

白内障は緑内障と異なり、老化現象のひとつであり、加齢が主な発症原因です。
高齢になると白内障になるため、緑内障と合併する方が増える傾向があります。
白内障とは
白内障とは、レンズの役割を担う水晶体が白く濁ってものが見えにくくなる目の病気です。
40代以降の発症率が高く、多くは加齢により白内障が発症しますが、アトピー性皮膚炎や目への外傷、糖尿病などにより発症することもあります。
80代になるとほぼ100%の方が白内障を発症することから、老化現象のひとつとして珍しい病気ではありません。
目がかすむ、もやがかかったように見える、光に敏感になる、視力が低下するなどの症状が現れます。
点眼薬で進行を抑制することもありますが、手術をすれば失明する可能性はほとんどありません。
緑内障と白内障の違い
緑内障と白内障の違いを、わかりやすく表にまとめました。
| 緑内障 | 白内障 | |
|---|---|---|
| 原因 | はっきりわかっていない 眼圧上昇・視神経の脆弱性・ 遺伝・白内障の進行・生活習慣など が考えられる | 加齢によるものが多い 他の病気との合併症・紫外線・外傷・アトピー性皮膚炎治療で使用するステロイド薬などが原因のこともある。 |
| 仕組み | 視神経が障害されて映像情報が脳へ上手く伝達されずに視野や視力に影響が出る | ピントを合わせる・視界をクリアに保つ役割を担う水晶体が白く濁り、視界や視力に影響が出る |
| 代表的な症状 | 視野欠損・視野狭窄・視力低下など | かすみ・もやがかかる 光がまぶしい・視力低下など |
| 治療の目的 | 現在見えている視野や視力の維持 | 見え方や視力の改善 |
| 治療方法 | 点眼治療・レーザー治療・手術 | 点眼治療・手術 |
| 検査方法 | 視力検査・眼圧検査・眼底検査・視野検査 屈折検査・前眼部検査・隅角検査・OCT検査 など | 視力検査・細隙灯顕微鏡検査 眼底検査 屈折検査 角膜形状解析 角膜内皮細胞検査 眼軸長測定検査 OCT検査 など |
緑内障は進行を抑制する目的で治療し、白内障は治療によって回復や改善が期待できることが、大きな違いとなります。
検査方法はクリニックによって異なりますが、他の病気の可能性を診断するためや、目の異常の原因を確定するために内容が変わることもあります。
緑内障と白内障の同時手術
緑内障の症状や種類にもよりますが、白内障との同時手術を行うことも可能です。
白内障手術に加えて低侵襲緑内障手術(MIGS)と呼ばれる傷が小さく負担が少ない手術や、線維柱帯切開術(トラベクレクトミー)などを行うケースが多いです。
白内障手術併用眼内ドレーン(iStent inject W)というMIGSの一種である手術は、医療用チタンでできた極小のデバイスを目の中に挿入して眼圧を下げる手術で、中等度までの緑内障の方に効果が期待できます。
緑内障と白内障の同時手術を行うことで、点眼薬の種類を減らしたり、新たな傷口を作らず負担を減らしたりできるメリットがあります。
しかし、手術の難易度が上がる、手術中の慎重な眼圧管理が必要になるなどのデメリットもあるため、経験と実績が豊富で信頼できるクリニックで医師とよく相談して、納得のうえで手術を受けましょう。
40代から定期的な眼科検診を受ける

緑内障は40代から発症率が上がる病気です。
早期発見が非常に重要で、早く治療を始めるほど視力を維持できる可能性が高まります。
緑内障を早期発見するためには、定期的な眼科検診が欠かせません。
40歳を過ぎたら、半年~1年ごとに眼科検診を受けることをおすすめします。
また、症状の進行度を把握するためにも、医師から指示された通院頻度を守りましょう。
眼科検診の内容
眼科検診で行う検査の内容はクリニックによって異なり、検査機器の導入があるかによっても変わります。
ここで紹介するのは、緑内障の発見を目的として行われることの多い検査です。
なお、緑内障の発見以外も含めた場合は、検査項目が増える・変わる可能性もあります。
眼圧検査
眼圧検査は眼球の硬さを測る検査で、緑内障を発見するために欠かせない検査です。
外から眼球に器具を当てる方法と、空気を当てる方法があり、クリニックに導入されている検査機器によりどちらの方法で検査するかは異なります。
眼圧は1日のなかでも時間により変化していて、季節や血圧などによっても数値が変わる可能性があるため、1度の検査で診断をするのは難しいものです。
複数回の眼圧測定を行いベースライン眼圧を設定することで、治療による効果を判断することもできます。
眼底検査
眼底検査では、視神経乳頭や網膜の状態を観察します。
緑内障を発症すると、視神経を束ねている視神経乳頭が圧迫されてへこみが大きくなったり、網膜視神経線維層の欠損が見られたりするため、確認が必要です。
多くの場合は瞳孔を広げる散瞳をして検査しますが、超広角眼底カメラでは無散瞳で網膜の広範囲を撮影できます。
瞳孔を広げない無散瞳で検査できる超広角眼底カメラならば、検査後の見えづらさや負担が少ないため、導入しているクリニックで検査を受けることを検討してみてはいかがでしょうか。
視野検査
視野検査は片目ずつ行い、視線を動かさずに見える範囲を測定します。
緑内障の主な症状である視野欠損の有無や、現在の見えている範囲の確認が可能です。
両目で見ると見えている方の目で欠けた部分を補ってしまいますが、片方ずつ検査を行うと左右の目で症状の差があるのかも確認できます。
光の出る場所が動く検査と、動かない検査があり、使用する測定機によって異なります。
屈折検査
屈折検査は、近視や乱視、遠視などの屈折異常を確認する検査です。
緑内障の発症要因や進行度には、近視の強さが関わっていることもあるため、裸眼の視力を測定する必要がある場合は行われます。
クリニックによっては屈折検査を行わないこともあります。
前眼部検査
前眼部検査とは、細隙灯顕微鏡や前眼部OCTなどの機器を使用して、角膜や水晶体、前房、虹彩などの状態を確認する検査です。
主に白内障の診断に必要とされる検査ですが、緑内障との併発時の診断や、他の目の病気が疑われるケースで行われることがあります。
また、補助レンズを併用することで、隅角や眼底の観察もできます。
隅角検査
隅角検査は、隅角を直接観察する検査で、閉塞型の診断に必要な検査です。
隅角の開き具合や癒着があるかどうか、新生血管の有無や線維柱帯の状態などがわかります。
急性緑内障発作のリスクを把握するためにも、隅角検査を行うことは緑内障診断において重要です。
点眼麻酔後に専用のコンタクトレンズを装着して、隅角鏡や前眼部OCTなどを使用して検査します。
OCT検査
OCT(光干渉断層計)検査は、緑内障の早期発見のために欠かせない検査です。
眼底検査だけでは判別できないくらいの微細な視神経乳頭や網膜の異常を撮影できるため、症状がほとんどない初期でも、緑内障を発見できます。
視神経乳頭のわずかなへこみや、網膜の層が薄くなっているなどを数値化して確認でき、早期発見が重要な緑内障の診断をするために役立ちます。
まとめ
緑内障は40歳を過ぎると発症率が上がり、加齢による要素もあると考えられる目の病気です。
慢性の場合は症状がゆっくり進行するため、数年~数十年かかって視野が少しずつ欠けていきます。
例えば40代で発症した場合、60歳になる頃には発症から約20年経っていることになり、適切な治療をしていなければ視野欠損が広がっている可能性があります。
緑内障は早期発見・早期治療が重要な病気で、きちんと治療を継続していれば失明せずに視力を維持することが可能です。
40歳を機に、定期的な眼科検診を受けて、緑内障を発症しても早期発見ができるように心がけましょう。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、OCT(光干渉断層計)検査や超広角眼底カメラによる無散瞳の眼底検査により、患者さんの負担が少ない検査を行っております。
白内障手術併用眼内ドレーンにも対応していて、緑内障の種類や進行度、健康状態によりますが、適応の場合は日帰り手術も可能です。
緑内障の進行度が知りたい方、手術を検討している方は、ぜひお気軽に『大阪鶴見まつやま眼科』へご相談ください。