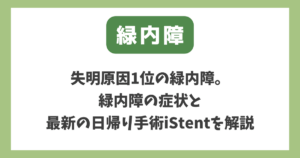緑内障は40歳以上で発症率が上がり、放置していると失明につながる恐れがある目の病気です。
しかし、きちんと治療を続ければ生涯視力を失わずに済む場合も多く、上手に付き合うことが重要です。
この記事では、緑内障の原因や種類、検査方法や治療について詳しく解説します。
どのような種類の緑内障があるのか、緑内障の原因などを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
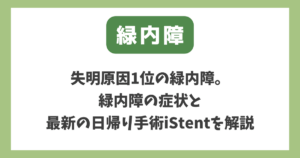
緑内障とはどんな病気?

緑内障とは、なんらかの原因により視神経が障害されて見え方や視力に影響が出る病気です。
以前は眼圧上昇が原因とされていましたが、眼圧が正常範囲内でも発症することから、はっきりした原因が判明していないのが現状です。
緑内障は目から入ってくる光を映像として脳に伝える視神経がダメージを受けて、情報が上手く伝わらなくなることにより、その部分の視神経が担っていた視界が欠けていきます。
障害を受けた視神経は元に戻ることはなく、欠けた視界も回復はできません。
緑内障は、日本における中途失明による視力障害の原因第一位であり、約40%を占めています。
(参照:岡山大学)
40歳以上になると約20人に1人は緑内障を患っていると考えられていて、珍しい病気ではありません。
しかし、実際に治療を受けている方は1割未満とされ、緑内障の診断すら受けていないまま放置されているのです。
緑内障は初期症状がほとんどなく、長い時間をかけて少しずつ視界が欠けたり、視野が狭くなったりして、見え方がおかしいと気づいたときには中期~後期に進行している可能性もあります。
自覚症状がなくても、40歳を過ぎたら定期的に眼科検診を受けて、緑内障の早期発見・早期治療に努めるのが重要です。
緑内障の種類

緑内障は大きく分けて以下のような種類があります。
原因がわからない原発緑内障と、原因がはっきりしている続発緑内障、小児期に発症した病気による小児緑内障です。
種類によって治療方法に注意が必要であったり、禁忌薬があったりするため、自分の患っている緑内障タイプを知っておくのが重要です。
原発開放隅角緑内障
原発開放隅角緑内障とは、眼球を満たす房水を排出するための隅角は開いているものの、その先の部分が詰まって房水が上手く循環できなくなり、眼圧が上昇するタイプの緑内障です。
眼圧が正常範囲内(10~20mmHg)でも発症する、正常眼圧緑内障も含まれます。
正常眼圧緑内障は若年層にも見られるため、40歳以下だからと油断せずに、検査を受けることをおすすめします。
一般的に緑内障と呼ばれるもののほとんどは原発開放隅角緑内障とされていて、日本人に多いタイプです。
眼圧の上昇にどこまで耐えられるかは個人差によるところが大きく、眼圧以外の検査を行い緑内障の診断をします。
症状の進行は緩やかで、数年〜数十年かけてゆっくり影響が出てきます。
原発閉塞隅角緑内障
原発閉塞隅角緑内障は、隅角が閉じたり狭くなったりして房水の排出ができずに水分が留まり、眼圧が上昇してしまうタイプの緑内障です。
慢性タイプの場合は、原発開放隅角緑内障と同様の進行スピードのことが多いですが、急性タイプの場合は注意が必要です。
急激に眼圧が上昇して急性緑内障発作が起こると、以下のような症状が見られます。
- 激しい目の痛み
- 目がかすむ
- 頭痛
- 吐き気・嘔吐
- 急激な視力低下 など
急性緑内障発作は放置すると数時間~数日で失明する恐れがあるため、すぐに眼圧を下げる処置が必要です。
眼科専門医でないと見逃してしまう可能性もあるため、救急で受診する場合は目の症状について必ず伝えるようにしてください。
続発緑内障
続発緑内障は、原因がわかっている緑内障です。
詳しくは後述しますが、他の目の疾患や全身疾患、薬物の使用などが原因で発症します。
進行が遅く、初期には自覚症状がないことがほとんどです。
続発緑内障も開放隅角型と閉塞隅角型があり、多くは開放隅角型で眼圧が高い傾向があります。
小児緑内障(発達緑内障)
小児緑内障は、生まれつき隅角や目に異常があり眼圧が上昇しやすく視神経が障害される病気です。以前は発達緑内障と呼ばれていました。
発症年齢は出生前から4歳以降の若年性まで幅広く、成長とともに発症することもあります。
目の形成異常や他の原因によるものの場合は、続発小児緑内障に分類されます。
緑内障の原因

緑内障の原因は、はっきりとは解明されていません。
眼圧の上昇は要因のひとつではありますが、正常眼圧でも緑内障を発症することから、眼圧だけが原因というわけではないと考えられています。
ここでは、緑内障の原因になる疑いがあるものについて、詳しく解説します。
眼圧上昇
眼圧の上昇は、緑内障の原因のひとつです。
眼球は房水と呼ばれる水分で満たされていて、房水の圧力により眼球のハリや球形を保っています。
房水が循環することで一定の圧力をキープしていますが、房水の排水が上手くいかずに循環が滞ると、眼球内の圧力が上昇してしまいます。
眼圧上昇により、視神経が圧迫されてダメージを受けると、約100万本ある神経線維が減少して脳へ映像情報を届ける機能が低下するため、視界の欠けにつながるのです。
どの程度の眼圧に耐えられるかは個人差が大きく、眼圧が高くても緑内障を発症しない方もいれば、正常範囲内でも緑内障の症状が現れる方もいます。
血流障害
血流が悪くなることにより、必要な栄養や酸素が届かなくなり、視神経が障害されるとも考えられています。
眼圧上昇がなくても、視神経へのダメージが大きいと機能が低下します。
極端な高血圧は動脈硬化につながり血流への悪影響がありますが、低血圧も目に必要な血液を送り出す力が弱まるため、注意が必要です。
ただし、高血圧の治療で急激に血圧を下げるのは、かえって目の負担になるため、緑内障のリスクが高まります。
また、睡眠時無呼吸症候群の方は、無呼吸になる時間に目への血流が滞る可能性があります。
緑内障だけでなく全身の健康状態を保つためにも、適切な治療を行いましょう。
遺伝的要因
緑内障が必ずしも遺伝するわけではありませんが、近親者に緑内障患者がいる場合はリスクが高まります。
先天性の目の異常により起こる小児緑内障の一部は、遺伝的要因があるとされていて、年齢に関係なく発症する可能性があります。
祖父母や両親など近い血縁者に緑内障患者がいる方は、症状がなくても定期的に眼科検診を受けて変化を見逃さないように心がけましょう。
加齢
加齢は緑内障の要因のひとつです。
40歳以上は発症率が上がり約20人に1人、60歳以上になると約10人に1人は緑内障を患っていると考えられています。
年を重ねるとともに、全身の機能は老化で低下していきます。
目の機能も例外ではなく、隅角の機能低下により房水の排出が上手くいかなくなったり、視神経が弱まりダメージを受けやすくなったりすることで、影響が出やすくなるのです。
加齢による緑内障はゆっくり進行するため、症状に気づきにくく発見が遅れる可能性が高いです。
40歳を過ぎたら半年~1年ごとの眼科検診を受けることを習慣にして、緑内障の早期発見を意識してください。
強い近視
強い近視がある方は、ない方と比較すると緑内障になるリスクが高いです。
-6.0D以上は強度近視とされていて、眼球が伸びて眼軸が長くなっています。
眼球が伸びていると目に負担がかかりやすく、視神経が障害される可能性が高まります。
視神経が束になって集まっている視神経乳頭が変形していると、眼圧の影響を受けやすく、視神経に直接ダメージを受けてしまいます。
強度近視の方は若年でも緑内障を発症する可能性があるため、リスクがあると理解したうえで眼科検診を受ける、見え方の変化に気を使うなどの注意が必要です。
続発緑内障の原因

続発緑内障は、原因がわかっている緑内障です。
原因になる疾患の治療を行い、眼圧のコントロールが必要かを判断していくことになります。
ここでは、続発緑内障の原因となる病気や薬物について、詳しく解説します。
他の目の疾患
続発緑内障を発症する原因になる他の目の疾患は、以下の通りです。
- ぶどう膜炎
- 網膜虚血性病変(糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症など)
- 偽落屑症候群
- ポスナーシュロスマン症候群
- 眼科手術後(角膜移植、白内障など)
- 水晶体脱臼・膨化
- 眼内腫瘍
- 小児球症
- 眼外傷など
これらの目の疾患により、合併症や後遺症として緑内障を発症することがあります。
目の病気の他にも、眼科手術や目への外傷が原因になる可能性も少なくありません。
回復しても、直後ではなく数年経ってから緑内障になる可能性もあるため、経過観察のための通院は最後まできちんと通い、その後も定期的に目の様子をチェックするようにしましょう。
全身疾患
続発緑内障の原因となる全身疾患は、以下の通りです。
- 糖尿病
- 脳疾患
- ベーチェット病
- サルコイドーシス
- アミロイドーシス など
糖尿病の進行は糖尿病網膜症を引き起こし緑内障の原因になることは知られていますが、他にも目の疾患以外の全身疾患により緑内障を患う可能性があります。
これらの疾患がある方は、治療とともに緑内障の発症を見逃さないために眼科検診を受けましょう。
薬物の使用
薬物の使用による副作用で眼圧に影響して、続発緑内障を発症することもあります。
アトピー性皮膚炎の治療のためのステロイド薬の長期使用や、ステロイド点眼薬の使用により眼圧が上昇することが原因です。
この場合、可能な限りステロイド薬を中止または減量して、必要なら緑内障点眼薬で眼圧をコントロールする治療を行います。
緑内障の検査

緑内障の診断をするためには、さまざまな検査が必要です。
クリニックにより、どのような検査を行うのかは異なります。
また、目の状態や他の病気があるかによって、検査が追加される場合もあります。
眼圧検査
眼圧検査は、緑内障の診断において欠かせない検査です。
眼球の硬さを測定する検査で、房水の働きがきちんと果たされているかがわかります。
眼球の表面に直接機械を当てる方法(接触型)と、空気を当てて測定する方法(非接触型)があり、クリニックが導入している測定機により異なります。
正常眼圧緑内障は、眼圧は正常範囲内ですが、それでも今より眼圧を下げるのが重要です。
眼圧は1日のうちでも数値が変わり、血圧と同様に変動していて個人差が大きいものです。
1度だけでなく、定期的に検査を行い長期的に変化を見ていくことになります。
眼底検査
眼底検査では、眼球の血管や網膜、視神経の状態を観察します。
視神経乳頭を観察することで、視神経乳頭陥凹や網膜視神経線維層欠損の状態、出血の有無などがわかります。
緑内障の診断のためには、視神経乳頭の状態を確認することが重要な要素です。
眼底カメラを使用する方法や、レンズで直接眼底を観察する方法などがあります。
視野検査
目を動かさずにどこまでの範囲が見えているかを確認する視野検査も、緑内障の診断や経過観察のために必要な検査です。
両眼で見ると欠けた視野を補ってしまうため、検査は片目ずつ行います。
初期から中期の緑内障では、静的視野検査で検査を行うことが多く、小さな光が見えたらボタンを押す方法で、中心付近の視野を調べるのに適している検査です。
広範囲の視野を測定するには動的視野検査で、視点を固定して動く光が見えたらボタンを押す検査を行います。
前眼部検査
細隙灯顕微鏡を使用し、目の表面から前方部分の撮影や数値解析を行う検査です。
角膜の形状や厚み、隅角の状態の測定などができます。
虹彩や水晶体などの3次元撮影ができるため、緑内障の早期発見に役立ちます。
隅角検査
緑内障の種類である開放型、閉塞型を判断することができるのが隅角検査です。
特殊な検査用のコンタクトレンズを装着して、隅角の状態を観察します。
眼圧が上がる原因が隅角であるかを診断することで、急性緑内障発作の危険性を確認できます。
OCT(光干渉断層計)検査
OCT(光干渉断層計)検査は、網膜や視神経乳頭を確認します。
視神経線維層の厚みを計測することもできる、重要な検査です。
眼底検査のみでは見つけられない、ごくわずかな視神経乳頭の異常も発見できる可能性があります。
初期の緑内障を発見するためには、OCT検査が役立ちます。
緑内障の治療

緑内障の治療は、薬物治療、レーザー治療、手術の3つがあります。
いずれも眼圧を下げるための処置となります。
治療方法は緑内障の種類によって異なり、開放隅角緑内障は、眼圧を下げる点眼薬が主な治療です。
点眼薬で眼圧が下がらなかったり、眼圧が下がっても症状が進行したりする場合は、レーザー治療や手術を行うことがあります。
閉塞隅角緑内障の治療は、レーザー治療を行い急性緑内障発作を予防することが重要です。
レーザー治療や手術を行っても、欠けた視野が回復するわけではありません。
特に初期の緑内障の方は自覚症状がない場合が多く、治療に対して消極的だったり、途中で治療を止めてしまったりするケースも少なくありません。
緑内障の治療は、今見えている範囲や視力を保ち、症状の進行を抑える目的で行われます。
点眼薬をきちんと使用して、定期的に通院を続けるのが、有効な治療方法です。
まとめ
緑内障の原因ははっきりとわかっていませんが、眼圧の上昇や血流障害、遺伝的要因、加齢、強い近視などがリスク要因として挙げられています。
いくつもの要因が絡み合って、緑内障の発症につながると考えられているのです。
また、原因がわかっている続発緑内障では、目の疾患や全身疾患、薬物などにより緑内障になるリスクが高まります。
病気の治療とともに、定期的な眼科検診を受けて、緑内障を始めとした目の健康を保てるように意識しましょう。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、幅広い治療方法の中から患者さんに適した治療をご提案できるように、丁寧な診察を心がけております。
低侵襲緑内障手術(MIGS)の日帰り手術にも対応しています。
緑内障の症状があって不安な方、眼科検診を受けたい方は、『大阪鶴見まつやま眼科』へお気軽にご相談ください。