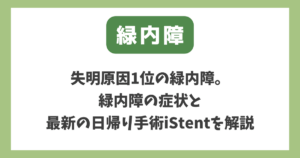緑内障の治療で、多くの場合、最初に選択されるのが目薬です。
目薬で眼圧を下げるのが治療の目的ですが、緑内障の治療で使用する目薬にはさまざまな種類があります。
処方された目薬がどのようなものなのか、副作用はあるのか、理解して治療するのが大切です。
この記事では、緑内障治療でよく使用する目薬の特徴や副作用、使用方法、注意点などについて詳しく解説します。
使っている目薬について知りたい方は、ぜひ参考にして下さい。
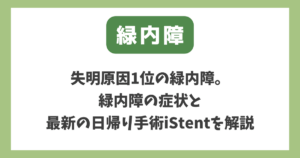
緑内障とは

緑内障とは、眼圧上昇やなんらかの原因によって視神経が障害され、視野欠損や視力低下の症状が現れる目の病気です。
日本の視覚障害の原因第1位で約40%を占め、40歳以上の20人に1人、70歳以上の10人に1人が患っているとされています。
(参照:岡山大学)
(参照:「日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査(通称:多治見スタディ)報告」日本緑内障学会)
眼圧の上昇は緑内障の要因のひとつではありますが、眼圧が正常でも緑内障を発症することもあり、はっきりとした原因は今のところわかっていません。
緑内障は早期発見・早期治療が重要な病気です。
40歳を過ぎたら、定期的な眼科検診を受けて、緑内障の兆候を見逃さないようにしましょう。
症状・分類
緑内障は視野欠損、視野狭窄、視力低下などの症状が現れるのが特徴です。
緑内障には種類があり、病型により症状の現れ方や治療方法、注意点も異なります。
| 分類 | 特徴 | 原因 |
|---|---|---|
| 原発開放隅角緑内障 | 目を満たす房水を排出する隅角は閉じていないが、その先で問題が生じて房水の排出が滞る。正常眼圧緑内障も含む。 | これといった原因がなくても発症する |
| 原発閉塞隅角緑内障 | 隅角が閉じるまたは狭まっている。急激に眼圧が上がる急性緑内障発作が起こる可能性がある。 | |
| 続発緑内障 | 他の疾患により引き起こされる。開放型と閉塞型がある。 | 原因となる他の目の病気や 全身疾患などがある |
| 小児緑内障 | 生後間もなく、成長とともに現れるなど個人差がある。 | 生まれつきの目の形成異常などがある |
日本人は開放隅角緑内障、特に正常眼圧緑内障が多く、症状はゆっくり進行します。
初期の自覚症状はほとんどなく、視野の欠けを自覚するのは中期以降で、治療の開始が遅れる傾向があります。
閉塞隅角緑内障は、慢性の場合は開放型と同様ですが、急性の場合は突然隅角が閉じて急激に眼圧が上がってしまう恐れがあるため注意が必要です。
激しい目の痛み、頭痛、目のかすみ、吐き気などが現れたら、急性緑内障発作かもしれません。
放置すると数日で失明してしまうこともあるため、緊急で眼圧を下げる処置が必要です。
続発緑内障は、原因となる他の疾患があり、治療をしながら対処していきます。
小児緑内障は遺伝的要素もありますが、生まれつきの目の形成異常や、他に患っている病気に関連するものなどもあります。
治療方法
緑内障の治療方法は、点眼治療、レーザー治療、手術です。
障害された視神経は元に戻ることはなく、視野や視力の回復はできません。
緑内障の治療は、今見えている範囲を守るため、症状を進行させない目的で行われます。
開放隅角緑内障の多くは、目薬を使用した点眼治療により眼圧を下げる治療が第一選択です。
正常眼圧緑内障であっても、現時点より眼圧を下げることで進行を抑制する効果が期待できます。
点眼治療で眼圧が下がりきらなかったり、症状が進行していく場合、レーザー治療や手術を行うこともあります。
閉塞眼圧緑内障は、急性緑内障発作の可能性がある場合は、レーザー治療や手術で発作を予防することが重要です。
治療方法はさまざまですが、症状や全身状態により適切な治療を医師とよく相談しましょう。
緑内障の治療で使用する目薬

緑内障の治療で使用する目薬には、多くの種類があります。
主に開放隅角緑内障の治療に用いられ、眼圧を下降させて進行を遅らせるのが目的です。
眼圧の下降とはいっても、どのような仕組みで治療の効果を及ぼすのかは、目薬の種類によって異なります。
ここでは、緑内障の治療で使用される目薬の特徴や副作用について、詳しく解説します。
プロスタノイド受容体関連薬
プロスタノイド受容体関連薬は、プロスタグランジンの受容体であるFP受容体に作用するものと、EP2受容体に作用するものがあり、特にFP受容体作動薬は緑内障の治療に多く用いられています。
特徴
房水に働きかけ、ぶどう膜強膜流出路からの房水の流出を促進して眼圧を下げる薬です。
多くのケースの緑内障で眼圧下降の効果が期待でき、処方の頻度が高い目薬です。
通常は1日1回夜寝る前に点眼し、24時間の眼圧コントロールができます。
ただし、EP2受容体作動薬は眼内レンズを挿入している場合は禁忌とされ、FP受容体作動薬との併用も推奨されていないため、注意が必要です。
プロスタノイド受容体関連薬は長期にわたる使用が可能なことから、長く治療を継続する必要がある緑内障にも適しています。
定期的な通院をして、眼圧の状態や副作用の有無など、経過観察しながら治療をすることが重要です。
副作用
副作用は以下のようなものがあります。
- 目の周りがくぼむ
- 色素沈着
- 充血
- 角膜障害
- まつ毛の異常成長 など
長期的な使用によって、目の周りにこれらの副作用が現れることがあります。
点眼後にあふれた液を拭き取ることで、副作用の軽減が期待できます。
交感神経β受容体遮断薬
交感神経β受容体遮断薬は、βブロッカーとも呼ばれ、体内のベータ受容体に作用して活性を抑制する目薬です。
特徴
房水の生成を抑制して、房水の量を減少させることにより、眼圧を下げる効果が期待できます。
通常1日2回の点眼が必要ですが、メーカーによって差があるため事前に確認しておきましょう。
交感神経β受容体遮断薬は、全身の副作用が現れる可能性があります。
気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患、コントロール不十分な心不全や糖尿病などの疾患がある方は使用できない場合もあるため、医師の指示に従いましょう。
副作用
副作用は以下の通りです。
- 充血
- 目のかゆみ
- 眼瞼下垂
- 異物感
- 結膜炎
- 動悸
- 頭痛
- 気管支喘息や気管支痙攣
- 血圧低下 など
必ずしも副作用が現れるわけではありませんが、交感神経β受容体遮断薬は全身的な副作用の可能性があります。
呼吸器や循環器の疾患がある方には使用できないこともあるため、医師とよく相談してください。
また、妊娠中や妊娠の可能性がある方にも使用できないケースがあります。
炭酸脱水酵素阻害薬
炭酸脱水酵素阻害薬は、体内の毛様体における炭酸脱水酵素の酵素活動を阻害する薬です。
酵素活動の阻害により、房水の生成を抑制して眼圧を下げる効果が期待できます。
特徴
房水が作られる量を減少させて、眼内の水分の量が減ることで眼圧の下降につながります。
元々は内服薬として使用されていて、目薬の他に注射薬などもあります。
1日に2~3回の点眼が必要となり、回数は目の状態やメーカーによって異なるため、医師の指示に従って使用しましょう。
長期間の眼圧コントロールに使用されることが多く、他の目薬との併用が可能です。
緑内障治療の第二選択として処方されるケースもあります。
ただし、重篤な腎障害や肝機能障害がある方は使用できないこともあるため、注意が必要です。
副作用
副作用は以下のようなものがあります。
- 目のかすみ
- 異物感
- 結膜炎
- 刺激 など
炭酸脱水酵素阻害薬で副作用が現れることはまれで、多くは一時的なものです。
目の違和感がある場合は、症状が落ち着くまでは運転や目を使う作業は控えましょう。
交感神経α2受容体遮断薬
交感神経α2受容体遮断薬は、交感神経α2受容体を刺激して、房水の生成抑制と排出を促して眼圧を下げる薬です。
特徴
交感神経α2受容体は、房水の産生と排出に関わっているため、点眼によりα2受容体を刺激することで、房水の量を減少させると同時に、ぶどう膜強膜流出路から房水の排出を促進する効果が期待できます。
点眼回数は通常1日2回行うのが一般的です。
総合的な眼圧管理に適しています。
ただし、重篤な心血管系疾患や不安定な高血圧症、血管迷走神経発作の既往歴がある方などには使用できないことがあるため、医師とよく相談しましょう。
副作用
副作用は以下の通りです。
- 散瞳
- 眼瞼挙上
- 白目の血管収縮による結膜蒼白
- アレルギー性結膜炎
- 口腔内の渇き
- 鼻の乾燥 など
交感神経α2受容体遮断薬による副作用はまれですが、症状がある場合は医師に相談しましょう。
Rhoキナーゼ阻害薬(ROCK阻害薬)
Rhoキナーゼ阻害薬はRock阻害薬とも呼ばれ、体内で細胞の生理機能や情報管理に関与している酵素であるRhoキナーゼを阻害する薬です。
特徴
Rhoキナーゼは房水の排出に関わっているため、Rhoキナーゼ阻害薬を使用することにより、線維柱帯からの房水の排出を促進し、眼圧を下げる効果が期待できます。
通常は1日2回の点眼が必要です。
Rhoキナーゼ阻害薬は血管拡張作用があり、一過性の副作用が現れる可能性があります。
特定の疾患に対する禁忌はありませんが、過去にRhoキナーゼ阻害薬の過敏症がある場合は医師に相談してください。
副作用
副作用は以下のようなものがあります。
- 結膜充血
- 結膜炎
- 眼瞼炎 など
Rhoキナーゼ阻害薬による副作用はまれですが、点眼後すぐ(30分~数時間程度)に一過性の充血が現れることがあります。
アレルギー反応が発生した場合は、すぐに医師に相談しましょう。
配合点眼薬
配合点眼薬は、複数の有効成分を組み合わせた目薬で、1つの目薬で複数の効果が期待できます。
これまで紹介した目薬は、眼圧を下げる効果が期待できますが、それぞれ異なる作用の仕組みです。
単剤での効果が不十分な場合、配合点眼薬と呼ばれる合剤の使用が検討されます。
配合点眼薬のメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 複数の点眼による待ち時間がなくなり さし忘れを防止できる | 自分の症状に合った合剤が 作られていないことがある(まだ種類が少ない) |
| それぞれの目薬に含まれている防腐剤による 角膜障害へのリスクを軽減できる | 1度点眼を忘れると、複数種類の点眼を忘れたことになってしまう |
| 複数本の目薬よりは薬代を減らせることがある | それぞれの成分ごとの副作用があるため、どの成分の副作用なのか判断が難しい |
複数の点眼をするには、間を空けてさす必要があるため、待ち時間が長くなり忘れてしまうことも珍しくありません。
何本も目薬をさすのが大変と感じている方には、メリットが大きいでしょう。
ただし、さし忘れのデメリットもあり、自分の症状や生活習慣、健康状態などを考慮して選択することが重要です。
緑内障の目薬の使用方法
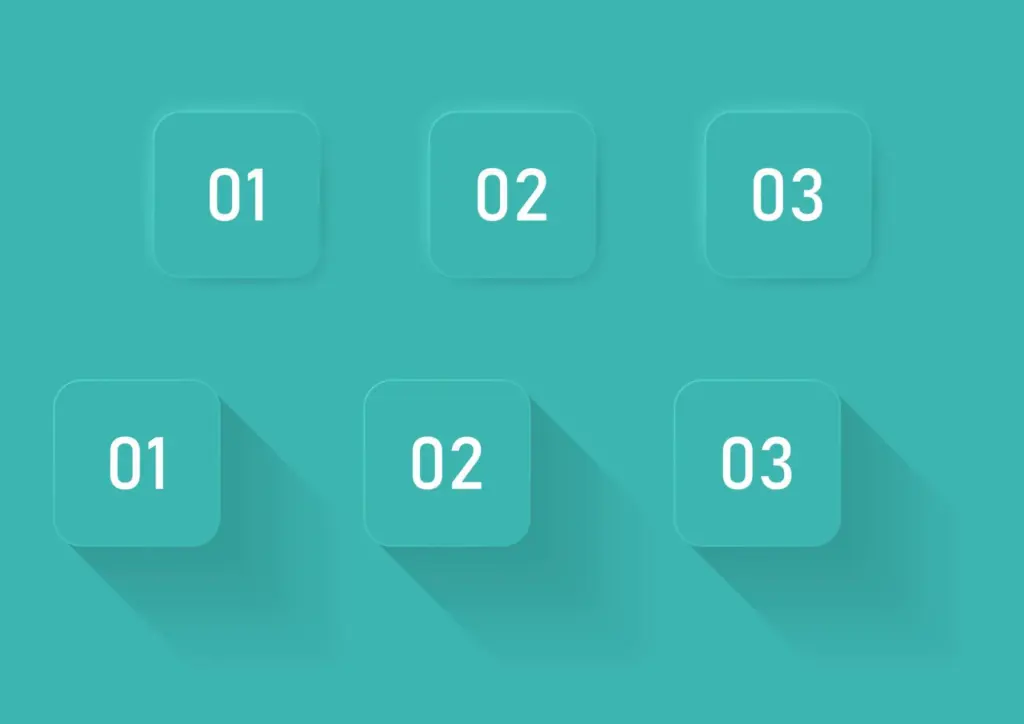
緑内障の目薬の効果を発揮するためには、正しい使用方法をすることが大切です。
ここでは、目薬の使用方法について、詳しく解説します。
目薬使用の手順
目薬を使用するにあたり、正しい手順を知っておきましょう。
- 手を洗って清潔にする
- 上を向き、下まぶたを引く
- まつげやまぶたに触れない位置から1滴を点眼する
- 目を閉じて1~2分間待つか、目頭を軽く押さえる(まばたきをしない)
- 目からあふれた点眼液をティッシュやガーゼで拭き取る
- 複数本の目薬を使用する場合は、5分以上空ける
多く点眼しても効果は変わらないため、1滴だけを正確に点眼しましょう。
点眼後はまばたきせずに目を閉じて、目薬が鼻やのどに流れるのを防ぎます。
目の周りに現れる可能性のある副作用を予防するためにも、あふれた液はきちんと拭き取りましょう。
なお、緑内障の目薬は複数本使用することもありますが、続けて点眼してしまうと目薬の成分が洗い流されてしまうため、5分以上時間を空けて使用してください。
保管方法
目薬は処方時に渡された袋に入れ、直射日光を避け、涼しい場所で保管しましょう。
目薬によっては「遮光して保管」「冷蔵保存」が必要なものもあります。(プロスタノイド受容体関連薬のキサラタン、レスキュラなどは冷蔵保存)
湿度は目薬の品質を損なう恐れがあるため、湿度の高い場所も避けてください。
また、使用期限はきちんと確認して、期間を過ぎたものは使用しないようにしましょう。
開封後は約1ヶ月以内の使用期限のことが多いですが、目薬によって異なるため、事前に確認が必要です。
コンタクトレンズについて
緑内障を患っていても、医師と相談して症状に影響がない場合は、コンタクトレンズの使用は可能です。
ただし、コンタクトレンズを装用したまま点眼はできません。
目薬の成分や防腐剤などがコンタクトレンズに吸収されて、時間が経ってから放出されることで、角膜炎を引き起こす可能性があるからです。
点眼後は最低5分、できれば15分以上の時間を空けてから、コンタクトレンズを装用します。
緑内障を発症してからのコンタクトレンズの装用は、装用時間や使用方法、定期的な通院による経過観察など、医師からの指示をきちんと守りましょう。
緑内障の目薬の注意点

緑内障の目薬を使用する際は、以下のような注意点があります。
長く治療が必要なため、気をつける点をきちんと確認しておきましょう。
用法を守る
点眼治療は、用法を守って使用するのが重要です。
目薬をさす順序の指示がある場合は、数字を袋に記入したり、紙に書いたりしておき、順序を守ってください。
一般的には液状を先に、ゲル状を後にさす方が、成分が流れず浸透しやすいとされていますが、医師や薬剤師の指示を守りましょう。
また、緑内障の目薬は回数や量を増やしても効果は増加せず、副作用が増すリスクがあります。
正しい用法を守ることで、緑内障の進行を抑える効果が期待できます。
使用禁忌の疾患を申告する
緑内障の目薬は、種類によって使用禁忌があります。
目や全身の緑内障以外の疾患がある方は、申告が必要です。
副作用のリスクを減らすためにも、疾患や服用している薬はきちんと医師に申告しましょう。
医師とよく相談して選択する
緑内障の治療は終わりがなく、一生継続しなければなりません。
目薬の種類により異なる使用方法や他の治療方法に、無理がないようにすることが重要です。
医師とよく相談して、症状やライフスタイル、他の病気など、さまざまなことを考慮しながら、適切な治療法を選びましょう。
まとめ
緑内障の治療で使用する目薬は、種類によってさまざまです。
作用する仕組みや効果、使用回数、使用方法も異なります。
緑内障の点眼治療は長く続くため、無理なく継続できる治療を選ぶことが重要です。
また、副作用のリスクを考えて、他の疾患がある方は申告をする必要があります。
緑内障の症状が進行するのを防ぎ、視力を維持するためにも、医師と相談をして自分に合った治療方法を行いましょう。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、緑内障を始めとする目の病気やお悩みに寄り添う治療を行っております。
丁寧な診察により、お一人おひとりにとってより良い治療をご提案させていただきます。
緑内障の目薬について知りたい方、治療方法に迷っている方は、ぜひお気軽に『大阪鶴見まつやま眼科』へご相談ください。