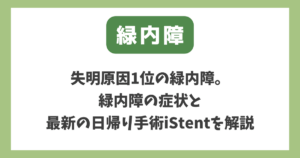緑内障にならないために、予防方法を知りたいとお考えの方は多いかもしれません。
しかし、原因がはっきりわかっていない緑内障には「これをすれば予防できる」という方法はないのです。
ただし、緑内障を発症するリスクを減らす、進行しないように対処することは可能です。
この記事では、緑内障のリスクを下げるさまざまな方法について詳しく解説します。
緑内障になりやすい生活習慣をやめたい方、目に良い栄養素を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
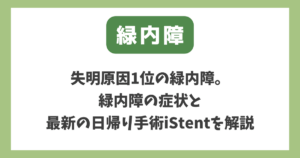
緑内障の予防方法とは?

緑内障は原因がはっきりしていないため、明確な予防方法はありません。
緑内障になりやすい要因は眼圧の上昇だけではなく、加齢や遺伝、強度近視、薬剤などがあり、複数の要素が絡み合って引き起こされると考えられています。
定期的に眼科検診を受ける
緑内障は早期発見・早期治療が重要な病気で、定期的な眼科検診を受けることが対策になります。
緑内障によりダメージを受けて損傷した視神経は元に戻らず、失った視野が回復することは難しいため、早期発見して症状を進ませないことが、非常に重要です。
初期の自覚症状がないうちに発見して治療を始めれば、視野欠損や視力低下などの進行を抑制して、視力を維持することが可能です。
自宅で片目ずつ見え方をチェックする、セルフチェックサイトで視野が欠けていないか確認するなども方法のひとつですが、症状が現れていないうちの発見は困難でしょう。
眼科で受ける検査では、ごく初期の視神経や目の組織の異常を発見することができるため、緑内障の早期発見に役立ちます。
緑内障の原因になる可能性がある病気を治療する
緑内障には種類があり、他の目の病気や全身疾患によって発症する続発緑内障は、原因となる病気を治療することで緑内障の予防が期待できます。
| 目の病気 | 全身疾患 |
|---|---|
| ぶどう膜炎 網膜虚血性病変(糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症など) 偽落屑症候群 ポスナーシュロスマン症候群 眼科手術後(角膜移植、白内障など) 水晶体脱臼・膨化 眼内腫瘍 小児球症 眼外傷など | 糖尿病 脳疾患 ベーチェット病 サルコイドーシス アミロイドーシスなど |
これらの治療を行うことにより、緑内障の発症や進行を抑制できる可能性があります。
ただし、目の外傷や手術後などは治療直後~数年後まで緑内障の発症のリスクがあるため、経過観察が欠かせません。
緑内障のリスクを下げる|生活習慣

緑内障の明確な予防策はありませんが、緑内障を発症しやすくなるリスク因子を避けることで、予防の一助になると考えられます。
ここでは、生活習慣に関する緑内障のリスク因子について解説します。
喫煙・過度な飲酒を控える
緑内障において、喫煙習慣や過度な飲酒はリスク因子になります。
喫煙で発生する活性酸素は、目の組織へダメージを与える可能性があります。
血管収縮によって血流が滞り、目に必要な栄養素や酸素が届きにくくなることで、視神経を障害する恐れもあり、喫煙は目にとって悪影響です。
また、過度な飲酒により激しい血圧の変化が起こると、血流に影響が出てしまいます。
このような血圧の乱れが頻繁に、そして長期間続くことで、視神経にダメージが蓄積することになるのです。
飲酒は適度な量をたまに楽しむ程度なら問題ありませんが、量が気になる方は医師に相談してみてください。
睡眠不足の解消
睡眠不足になると、体内の活性酸素が増大して酸化ストレスの発生により目の組織を傷つけてしまう恐れがあります。
また、良く眠れないと感じている方は睡眠時無呼吸症候群の可能性もあるため、いびきが大きい、夜中に何度も起きる、寝ている間に呼吸が止まっていると指摘されたなどがあったら、検査を受けてみましょう。
睡眠時無呼吸症候群で呼吸が止まっている間は目や脳への血流が弱くなり、視神経が障害を受けやすくなったり、眼圧が上がりやすくなったりしています。
良質な睡眠は目だけでなく全身の健康にも良い影響があると考えられているため、睡眠の環境を改善する対策をしましょう。
適度な運動習慣
適度な運動習慣は血流を改善して、眼圧の調整や全身の健康状態も整えられます。
ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を取り入れるのがおすすめです。
ただし、息を止めて力を入れるような運動(筋トレや重りを使用するトレーニングなど)の無酸素運動は、眼圧が上昇してしまうリスクがあるため避けましょう。
目を酷使しない
スマートフォンやゲーム、パソコンなどを長時間見ていると、目の負担になってしまいます。
これらが直接緑内障の発症リスクになるわけではありませんが、目が疲れて眼精疲労や近視が進む可能性があります。
また、読書や書き物、暗い部屋での作業なども、長い時間続けるのは目に悪影響を与える可能性があるため避けましょう。
こまめな休憩を取って目を休ませる時間を作る、遠くを眺めて緊張した目元をリラックスさせるなど、目の負担を軽減するような対策を考えてみてください。
バランスの良い食事
緑内障になっても、食べてはいけない食材などはありません。
基本的になんでも食べられますが、バランスの良い食事を意識しましょう。
脂質や糖分、塩分の多い食事を続けていると、糖尿病や高血圧、肥満などを始めとした生活習慣病のリスクが上がり、これらの病気は緑内障のリスクも上がる要因となります。
また、血圧や血糖値が高いと眼圧も高くなると考えられているため、注意が必要です。
偏った食事や好きなものだけを食べるのは控え、バランス良くさまざまな食材を摂るように心がけましょう。
ストレスを溜めない
ストレスを溜めすぎると、自律神経の乱れにつながり、血圧や血流に影響が出てしまう可能性があります。
血圧は低すぎても血流が弱くなって低酸素状態になりやすく、緑内障だけでなく他の病気を防ぐためにも適度な血圧を保つことが大切です。
過剰なストレスによって睡眠不足や頭痛、交感神経への影響などもあり、全身の健康に悪影響を及ぼします。
ストレスはさまざまな病気の元になると考えられているため、緑内障にとってもよいとは言えません。
眼圧上昇につながる姿勢・行為・服装に注意する
緑内障の発症要因のひとつに、眼圧上昇が挙げられます。
眼圧が上がるような姿勢や行為、服装には注意が必要です。
下を向く姿勢や高い枕、うつ伏せ寝は首への血流が悪くなって、眼圧が上がりやすくなるため避けましょう。
猫背に気をつけ、背筋を伸ばして顎を上げて少し上を向く姿勢を意識してください。
エステや整体、マッサージなどでうつ伏せの姿勢で長く施術を受けるものもあるため、これらが習慣になっている方は気をつけましょう。
逆立ちは通常の生活をしていればあまりしない姿勢ですが、回転するジェットコースターでは逆さになるため注意が必要です。
目を強く押したり、重い物を持ち上げるときに息を止めたりするのも、瞬間的に眼圧が上がりやすくなります。
また、ネクタイを強く締めすぎる、きついタートルネックの服など、首元を締め付ける服装も眼圧上昇につながるため、避けましょう。
緑内障のリスクを下げる|栄養素

緑内障で食べてはいけない食材はありませんが、過剰な塩分や糖分、脂質などは控えましょう。
ここでは、目に良いとされるおすすめの栄養素を紹介します。
栄養が偏らないようにバランス良く食生活に取り入れてみましょう。
ビタミンA
ビタミンAは眼球の奥にある角膜や粘膜を保護し、涙の水分量を保ちます。
目のビタミンとも呼ばれ、目の健康にとって重要な栄養素です。
- レバー
- ウナギ
- 乳製品(チーズ、バターなど)
- 卵
- 緑黄色野菜(ほうれん草、春菊、小松菜、ブロッコリー、かぼちゃなど)
ビタミンB
ビタミンBは、目の細胞の新陳代謝を促し、視神経の働きを高め眼精疲労の回復などの効果が期待できます。
不足すると目が疲れやすくなり、視神経にも負担がかかってしまうため、積極的に取り入れましょう。
- 豚肉
- ウナギ
- レバー
- 貝類
- にんにく
- 赤身魚
- 玄米
- 豆類(大豆、枝豆、小豆、豆腐や納豆などの大豆製品)
ビタミンE
ビタミンEは抗酸化ビタミンとも呼ばれ、目の老化防止や疲れ目の改善に役立ちます。
ドライアイが気になる方にもおすすめの栄養素です。
- かぼちゃ
- アボカド
- ニラ
- 卵
- ナッツ類
- 豆乳
- 玄米
- オリーブオイル
ルテイン
ルテインは抗酸化作用があり、ブルーライトや紫外線を吸収し、有害な光線から目を保護する働きがあります。
元々目の中に存在している栄養素ですが、加齢により減少していき、不足すると緑内障や白内障のリスクが上がると考えられています。
- ほうれん草
- ブロッコリー
- かぼちゃ
- グリンピース
- にんじん
- パプリカ
- アボカド
- 他、緑黄色野菜
アントシアニン
アントシアニンは赤や青紫の天然色素を含むフラボノイドの一種で、抗酸化作用があります。
目の老化防止や目の周りの筋肉が緊張するのを緩和して、緑内障の予防にもつながります。
水に溶けやすく長時間の効力はないため、毎日少しずつ食事から摂取するのを意識しましょう。
- ベリー類(ブルーベリー・カシスなど)
- アサイー
- 黒豆
- ナス
- むらさきいも
- ぶどう
オメガ3脂肪酸
オメガ3脂肪酸は、ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)などの細胞形成や血液をさらさらにする成分が含まれ、視神経への血流改善効果が期待できます。
体内で合成できない必須脂肪酸で、適量を摂取することでマイボーム腺の油分を正常化してドライアイや生活習慣病の予防にも役立つ栄養素です。
- サンマ
- 鮭
- サバ
- イワシ
- たらこ
- いくら
- アマニ油
アスタキサンチン
アスタキサンチンは赤色の天然色素で、強力な抗酸化作用があります。
眼精疲労や目の老化を予防する効果が期待できます。
抗酸化の力が弱まると緑内障の症状が進んでしまう可能性が高まるため、意識して取り入れるのがおすすめです。
- 鮭
- いくら
- エビ
- カニ
カテキン
お茶に含まれるカテキンは、抗酸化力が高いフラボノイドの一種です。
目の老化防止にも役立ち、ビタミンCやビタミンEの抗酸化作用を高める効果も期待できます。
- 緑茶
- 紅茶
- ほうじ茶
- 番茶
- 烏龍茶 など
なお、粉末で摂取しても栄養素は摂れます。
カカオポリフェノール
カカオポリフェノールは、特に高カカオチョコレートの強い抗酸化作用が目に良いと考えられています。
一酸化窒素の合成を促進し、血圧下降や血管が詰まるのを予防するなどの効果が期待できます。
ミルクチョコレートやホワイトチョコレートはカカオの含有率が少ないため、カカオ70%以上の高カカオチョコレートでないと有効とは言えません。
ただし、ダークチョコレートであっても脂質は多く、ポリフェノールは体内に留まらないため、小分けの継続摂取をしましょう。
1日20〜25gほど、5回くらいに分けて食べるのがおすすめです。
予防が難しい急性緑内障発作

症状がゆっくり進む慢性の緑内障は、これまで紹介してきた方法で進行を遅らせたり、発症リスクを減らせる効果が期待できますが、急性の緑内障はその限りではありません。
ここでは、予防が難しい急性緑内障発作について、詳しく解説します。
急性緑内障発作とは
急性緑内障発作は、緑内障の種類のなかでも閉塞隅角緑内障で起こる可能性があります。
隅角(眼球を満たす房水が循環するための排出口)が、突然閉じて眼球内に房水が溜まって眼圧が急激に上昇し、視神経が圧迫され、以下のような症状が現れます。
- 激しい目の痛み
- 目のかすみ
- 充血
- 急激な視力低下
- 激しい頭痛
- 吐き気
- 嘔吐 など
このような症状は急性緑内障発作の可能性があり、緊急で眼圧を下げる必要があります。
放置すると数時間~数日で視神経の多くがダメージを受けて視野欠損が起こり、失明に至る可能性が高いです。
急性緑内障発作は目の症状を伴う場合が多いため、頭痛や吐き気などの症状だけでなく、目に異常があることを必ず伝えてください。
脳や心臓の疾患に間違われて眼科的処置が遅れてしまい、そのまま視力を失ってしまうケースも珍しくありません。
急性緑内障発作を予防するには?
急性緑内障発作を予防するためには、閉塞隅角緑内障の治療を行うことが重要です。
しかし、他の種類の緑内障を含め眼科検診を受けていないと発見が難しいため、突然の発作で初めて閉塞隅角緑内障を患っていたと知る方も少なくありません。
40歳を過ぎたら緑内障の発症率が上がるため、半年~1年ごとに眼科で検査を受けて、緑内障の早期発見を心がけましょう。
閉塞隅角緑内障は、慢性であれば症状は時間をかけて進行していきますが、急性緑内障発作が起きる可能性があるため、治療が必要です。
レーザーで目の虹彩に小さな穴を開けて房水が通るようにする治療もありますが、近年は白内障の手術を行うケースも増えています。
白内障の進行が一因となっていることも多く、白内障の手術で眼内レンズを入れると房水が流れやすくなり、結果として眼圧が下がるのです。
また、白内障と緑内障の同時手術であるiStent injectWでは、医療用チタンで作られた小さなデバイスを挿入することで房水の排出を助けて緑内障の進行を抑制する効果が期待できます。
低侵襲緑内障手術(MIGS)の一種であり、目の内側からのアプローチで傷口が小さく手術時間も短く済むため、負担が少ない手術方法です。
まとめ
原因がはっきりしていない緑内障は、明確な予防方法がありません。
しかし、リスク要因に注意することで、緑内障の発症や進行を抑える効果は期待できます。
特別に我慢したり、してはいけないことが増えたりするわけではありませんが、健康的な生活を意識して生活することを心がけましょう。
予防が難しい急性緑内障発作は処置が遅れると失明に至る可能性が高いため、定期的に眼科検診を受け、必要な場合は手術を行うことで、発作が起こるのを予防できます。
緑内障の症状である視野欠損や視力低下が起こると、元に戻すことはできません。
制限なく日常生活を送り、QOLを保つためにも、緑内障のリスクを減らす方法を試してみてはいかがでしょうか。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、患者さんお一人おひとりのライフスタイルに合わせて、適した治療法をご提案させていただきます。
緑内障と白内障の日帰り手術に対応し、手術には高解像度の手術顕微鏡を使用して小さな切開で行い、術後の回復の早さも大切にしております。
緑内障の手術を検討している方、眼科検診を受けたい方は、ぜひお気軽に『大阪鶴見まつやま眼科』へご相談ください。