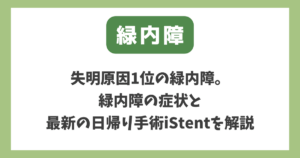緑内障になったら、してはいけないことが増えて我慢が必要なのかと、不安になってしまう方も少なくありません。
しかし、「してはいけないこと」はそう多くはなく、注意すべき点さえ知っていれば、日常生活を今まで通りに送ることが可能です。
この記事では、緑内障になったら避けたい習慣や気をつける飲食物、注意することについて詳しく解説します。
緑内障になっても楽しみを諦めないためにも、ぜひ参考にしてください。
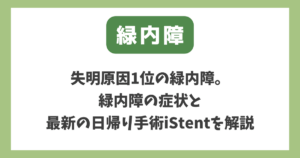
緑内障とは?
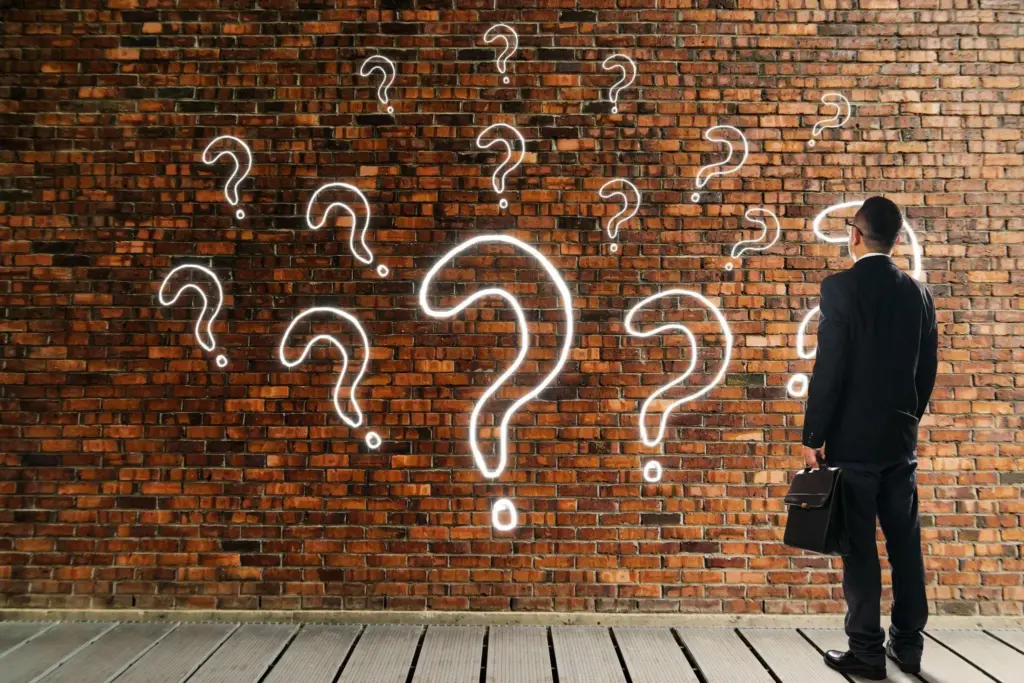
緑内障とは、なんらかの原因により目で見た情報を脳に伝える視神経が障害されて、その部分の視野が欠けたり、視力が低下したりする目の病気です。
眼圧の上昇により視神経に圧力がかかることも緑内障発症の要因のひとつですが、はっきりとした原因はわかっていません。
2019年の調査によると、日本の視覚障害の原因第1位は緑内障で、約40%を占めています。
(参照:岡山大学)
緑内障は徐々に症状が進んでいき、初期は自覚症状がほとんどなく気づきにくいため、見え方の異常を自覚したときには視野欠損が広がってしまっていることも珍しくありません。
数年~数十年かけて進行して、適切な治療をせずに放置していると、いずれ失明する可能性もある病気です。
元には戻せないため早期の治療や対策が重要
緑内障によりダメージを受けて機能を失った視神経は、元に戻すことができません。
つまり、視野欠損した部分が再び見えるようになることはないのです。
緑内障の治療は「現在の視力を維持する」ために、視神経が受ける障害を減少させて進行を抑制することを目的とします。
緑内障は時間とともに症状が進み、見える範囲が狭くなっていきます。
より多くの視神経を守って視野を保てる可能性が高めるためにも、早期発見・早期治療が非常に重要です。
自分の緑内障のタイプ・分類は?
緑内障にはいくつかのタイプがあり、気をつけるべきことが異なるため、自分がどのタイプの緑内障なのかを把握しておきましょう。
- 原発開放隅角緑内障(正常眼圧緑内障を含む)
- 原発閉塞隅角緑内障(急性緑内障発作に注意)
- 続発緑内障(原因となる他の疾患がある。開放型と閉塞型がある)
- 小児緑内障(先天的な目の形成異常などによる)
大きく4つに分類されますが、その中でも開放型と閉塞型などのタイプ別に細分化されています。
このうち、隅角(眼球を満たす房水を排出する部位)が閉じたり狭くなったりして起こる閉塞隅角緑内障は、急性緑内障発作のリスクがあるため注意が必要です。
急性緑内障発作は、激しい目の痛みやかすみ、頭痛、吐き気、視力の低下などの症状が現れて、緊急で処置が必要です。
放置していると、一晩~数日で失明に至る可能性もあります。
また、後述しますが、閉塞隅角緑内障は抗コリン薬が禁忌であり、他にも気をつけなければいけない薬剤もあるため、自分がどのタイプなのかは知っておかなければなりません。
自己判断で市販薬を服用したり、他の疾患で処方される薬剤の成分を確認したりして、慎重に対応する必要があります。
緑内障になったらしてはいけないこと

緑内障と診断されたら気をつけるべきなのは、眼圧を上昇させる行為をしないことです。
ここでは、眼圧上昇や目に負担になる可能性がある生活習慣について、詳しく解説します。
長時間のうつむき姿勢
長時間のうつむき姿勢は、眼圧の上昇につながるため避けましょう。
デスクワークや読書、ゲーム、スマートフォンなど、下を向く姿勢を長い時間続けていると、眼圧が上がりやすくなったり、首から目への血流が悪くなったりしてしまいます。
姿勢に注意し、こまめに休憩して目を休めるように意識しましょう。
過度な飲酒
過度な飲酒は血流に影響するため、控えましょう。
飲酒により激しい血圧の変動が起こると、目に必要な栄養や酸素が届きにくくなったり、眼圧のコントロールが乱れたりして、緑内障の症状が進行してしまうリスクがあります。
毎日のように大量の飲酒を繰り返すのは、緑内障だけでなく全身の健康にも悪影響です。
適量をたまの楽しみにする程度に留め、過度の飲酒はしないように心がけてください。
喫煙
喫煙は血管が収縮して視神経へのダメージが蓄積してしまうため、緑内障の症状を進行させる要因になります。
また、タバコの成分であるタールは活性酸素の発生を増大させ、血管機能の障害が起こります。
活性酸素の発生により血流が悪くなると、目の組織にも負担がかかってしまうと考えられます。
緑内障になりやすい要因でもあり、動脈硬化や他の病気を引き起こすこともあるため、健康状態を保つためにも禁煙を検討しましょう。
乱れた食生活
食生活の乱れは生活習慣病を引き起こす可能性も高まり、肥満や高血圧、糖尿病などになると血流に悪影響を及ぼします。
偏った食事や濃い味付けは、塩分や糖質、脂質などの過剰摂取にもつながり、緑内障だけでなくさまざまな病気を発症するリスクも上がります。
また、過剰な水分摂取は眼圧を上げてしまうため、大量の水分を一気に摂るのは控えて、少量ずつこまめな水分補給をするように意識しましょう。
ストレスを溜める
ストレスが溜まると、自律神経が乱れて血流が悪くなったり、眼圧のコントロールが不安定になったりすることがあるため、注意が必要です。
また、ストレスが増えると睡眠不足になる傾向もあり、活性酸素の発生を促進して目の組織へのダメージにつながる可能性もあります。
視神経への負担を減らすためにも、リラックスできる方法を見つけましょう。
眼圧上昇につながる習慣
緑内障にとって、眼圧を上昇させないように気をつけることが大切です。
睡眠姿勢は目に負担が少ない仰向けを意識したり、血流を妨げないように低い枕を使用したりして、工夫しましょう。
また、暗い場所では瞳孔が拡大しやすく、眼圧に影響があると考えられます。
作業環境を見直し、明るい場所に移動する、明るさを確保できる電球に変えるなどを検討してください。
緑内障になったら気をつけたい飲食物

緑内障になったら、食べられないものがあるのかと心配な方もいるかもしれませんが、基本的に禁止されている食べ物・飲み物はありません。
飲食物が直接緑内障の進行や発症の原因になることはなく、バランスを考えて偏りのない食生活を意識するのが大切です。
ただし、摂り方に気をつけるものはあります。
ここでは、食べたり飲んだりするときの量に気をつけるものを紹介します。
糖質
糖質の過剰摂取は、緑内障の発症や進行のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。
砂糖だけでなく、小麦粉でできたパスタやうどん、白米にも糖質は含まれているため、食事全体の糖質量を見直しましょう。
過剰な糖質を摂取し続けていると血糖値に影響して、糖尿病を始めとした生活習慣病にかかりやすくなるリスクが高まります。
糖尿病を発症すると、血液に含まれる糖分が吸収できなくなり、血管の詰まりや出血が起こりやすくなるため、目にも影響が出てきます。
糖尿病が進行すると糖尿病網膜症を発症することがあり、緑内障の原因となります。
肥満や高血圧になるリスクもあり、動脈硬化は血流の問題に直結して視神経が障害され、緑内障にとっても良くありません。
ただし、糖質を全く摂らないのはエネルギーの不足や栄養バランスが崩れてしまうことにつながります。
白糖をきび砂糖やオリゴ糖に変えたり、主食を玄米にしてみたりして、適切な量の良質な糖質を摂取しましょう。
脂肪分
脂肪分は身体のエネルギー源である重要な栄養素ですが、摂りすぎは控えましょう。
過剰な脂肪分の摂取は、肥満や多くの生活習慣病になる可能性があり、さまざまな病気を発症する原因になりかねません。
例えば肥満度が上がると血圧や血糖値も上がり、高血圧や糖尿病のリスクが上昇していきます。
なお、血圧や血糖値の上昇と比例して、眼圧が上がりやすくなると考えられているため、肥満の解消は緑内障の進行抑制にも効果が期待できます。
脂質の摂取量は年齢や性別により変わるため、自分の適正量を把握して、バランスの良い食事を心がけましょう。
塩分
塩分の摂りすぎは高血圧になりやすく、血流や血管に影響を与えます。
極端な高血圧は血流が増えて目への負担になり、治療のための薬の服用で急激に血圧が下がると目への血流が滞り、視神経にダメージを受けてしまう可能性が高まります。
日本人は和食に使われる調味料や漬物などから、塩分を過剰摂取しがちな食生活をしている方が少なくありません。
醤油や味噌は減塩のものを使用したり、出汁を活用して薄味を心がけたりして、塩分を減らした食事を意識しましょう。
カフェイン・アルコール
カフェインやアルコールは、適量ならば問題ないとされていますが、過剰摂取には注意が必要です。
1日を通してカフェインを含む飲み物(コーヒーや紅茶など)を飲み続けると、眼圧の上昇につながる恐れがあります。
アルコールの摂りすぎは、血圧が乱れて目の負担になってしまう可能性が高まります。
完全にやめる必要はありませんが、適量を意識して飲みすぎないように注意しましょう。
緑内障になったら注意すること

緑内障になっても、日常生活は大きく変えずに過ごせます。
ただし、QOL(生活の質)を保った生活を続けるためにも、以下のようなことに注意してください。
抗コリン薬は閉塞隅角緑内障の禁忌薬
閉塞隅角緑内障の方は、抗コリン薬が禁忌薬です。
抗コリン薬は以下のような薬剤に含まれます。
- 抗不安薬
- 抗てんかん薬
- 消化性潰瘍治療薬
- 抗ヒスタミン薬
- 循環器治療薬
- 催眠鎮静剤
- 統合感冒剤
- 排尿障害治療薬
- 抗パーキンソン剤
- 気管支拡張剤 など
抗コリン薬には瞳孔を広げる作用(散瞳)があり、隅角の閉塞が促進されて急性緑内障発作を引き起こすリスクがあります。
一部の風邪薬などにも含まれていて、きちんと成分を確認していないと誤って服用してしまう可能性があるため、注意が必要です。
閉塞隅角緑内障の方は、必ず担当の医師に「閉塞隅角緑内障である」と申告してください。
なお、開放隅角緑内障の方には禁忌薬ではありませんが、慎重投与とされています。
他の疾患による薬に注意
アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎など、他の疾患でステロイド薬剤を使用する際は注意が必要です。
ステロイド剤は、緑内障の種類にかかわらず眼圧が上昇する可能性があります。
点眼薬や内服薬、軟膏、点滴などのステロイド剤が処方される場合は、医師とよく相談して使用を控えるか、定期的な眼圧検査を行い経過を慎重に観察するなどの対応をしなければなりません。
緑内障のリスクがある疾患の治療
続発緑内障のように、原因となる他の疾患がある場合は、治療をすることで緑内障の悪化を防げる可能性があります。
ぶどう膜炎や網膜剥離、眼内腫瘍、目への外傷など、緑内障の進行に影響する可能性のある病気は治療とともに経過観察を行いましょう。
また、緑内障以外の目の疾患についても、並行して治療を行うことが重要です。
糖尿病や睡眠時無呼吸症候群、高血圧・低血圧などは緑内障だけでなく他の病気を引き起こす原因にもなることから、全身の健康を保つためにもしっかり治療しましょう。
日常生活を大切にする
緑内障になったら、さまざまなことが変わってしまうのではと不安になってしまうかもしれませんが、日常生活で過度に気をつけすぎることはありません。
失明するのではと心配しすぎて外出しなくなったり、目に悪いと思われることを一切しなかったりして、極端に生活を変えてしまう方もいますが、基本的に今まで通りに過ごしてください。
適度な運動や外出、趣味、食事、嗜好品など、ほとんどのものには制限はありません。
注意点は意識したうえで、ストレスを溜めないためにも好きなことを諦めずに過ごしましょう。
ただし、きちんと指示された通院・治療を続けていることが前提となります。
通院・治療を続ける
緑内障と診断されたら、定期的に通院を続け、毎日眼圧を下げるための点眼をするのが重要です。
緑内障は初期には自覚症状がほとんどなく、せっかく早期発見できても治療をやめてしまう方も少なくありません。
しかし、放置していると少しずつ症状が進行して、視野の欠けを自覚する頃には生活に支障が出ている可能性も高いのです。
障害された視神経は元に戻ることはなく、見え方が回復することはありません。
緑内障の治療は今見えている範囲を維持して、症状を進行させないことが目的です。
改善しないならと治療に積極的ではない方もいますが、きちんと治療を続けていればほとんどの場合、一生視力を保ったまま、自分の目で見続けることが可能です。
失明する前に発見できたことを前向きにとらえて、通院と治療を続けていきましょう。
まとめ
緑内障になったらしてはいけないことは、眼圧を上げる習慣や病気の原因になり得る食事です。
直接緑内障に関わらないように感じても、全身の健康を保つことは目の健康にもつながります。
極端な制限や我慢は必要ありませんが、健康的な生活を心がけましょう。
また、緑内障の治療は終わりがなく、自覚症状がないと途中でやめてしまう方が多く問題となっています。
生涯にわたって視力を維持するためにも、定期的な通院と治療を継続することが重要です。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、患者さんのライフスタイルに合わせて、丁寧に話し合い適切な治療をご提案いたします。
低侵襲緑内障手術(MIGS)の日帰り手術にも対応しています。
緑内障の診断を受けて不安な方、通院先をお探しの方は、ぜひ『大阪鶴見まつやま眼科』へお気軽にご相談ください。