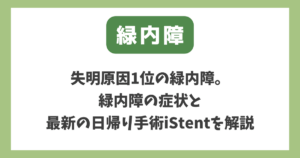「自分は緑内障になりやすいのか」を不安に感じている方は少なくありません。
緑内障を発症する原因は明確には判明していませんが、なりやすい要因はいくつかわかっています。
この記事では、緑内障になりやすいとされるリスクファクターについて生活習慣、他の疾患、その他の要因に分けて詳しく解説します。
緑内障になりやすい要因を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
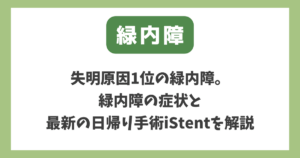
緑内障とは?原因や分類

緑内障とは、目で見た情報を脳に伝える役割を担った視神経がなんらかの原因によって障害されて、映像が上手く伝わらなくなる目の病気です。
目を満たす水分である房水の排出が滞ることで眼圧が上がって、視神経に圧力がかかることも要因のひとつではあります。
しかし、眼圧が正常範囲内(10mmHg~20mmHg)でも緑内障を発症するため、眼圧だけが原因ではなく、はっきりとした原因は判明していません。
詳しくは後述しますが、眼圧の他にも遺伝的要素や加齢、強度近視が原因になり緑内障を患うケースもあります。
緑内障は大きく分けて以下の4つに分類されます。
- 原発開放隅角緑内障
- 原発閉塞隅角緑内障
- 続発緑内障
- 小児緑内障
原発緑内障は原因不明な緑内障の分類で、隅角の状態により分けられます。
日本人に多い正常眼圧緑内障は、原発開放隅角緑内障に含まれます。
原発閉塞隅角緑内障は、急激に眼圧が上がり、すぐに適切な処置をしないと失明する恐れのある「急性緑内障発作」が起こる可能性があるため、注意が必要です。
続発緑内障は疾患の影響で発症する緑内障で、開放型と閉塞型があります。
小児緑内障は生まれつきの目の形成異常(続発小児緑内障)や、成長とともに発症するケースもあります。
緑内障のリスクファクター|生活習慣

緑内障のリスクファクターとして、いくつかの生活習慣が挙げられます。
喫煙習慣
喫煙は血管の収縮が起こり、目への血流に悪影響を及ぼします。
目に必要な栄養や酸素が十分に供給されず、視神経の障害につながるのです。
また、喫煙は活性酸素を発生させて、目の組織にダメージを与えてしまう恐れもあります。
長期間の喫煙習慣がある方は緑内障になりやすいため、注意が必要です。
過度の飲酒
過度の飲酒は血圧の乱れを引き起こし、目に影響する可能性があるため、注意が必要です。
血圧の上昇だけでなく、急激な血圧の下降も目に必要な栄養や酸素が不足することがあります。
毎日大量の飲酒をする方は血圧の上下が激しくなり、長期的に続けると目に悪影響を与えてしまうリスクを高めます。
適度な量と頻度を心がけ、過度の飲酒を控えるように心がけましょう。
食生活の乱れ
食生活の乱れは、生活習慣病への影響はもちろん、緑内障のリスクファクターになります。
カフェインの過剰摂取は、一時的に眼圧が上がりやすくなるため注意が必要です。
1日中カフェインが含まれる飲み物(コーヒーや紅茶など)を飲み続けるのは避けましょう。
また、塩分や脂質、糖質の摂りすぎは肥満や高血圧の原因にもなり、血流が悪化してしまう可能性があります。
全く摂らないのも身体に良くないため、食材や栄養素の偏りを減らし、バランスの良い食事を意識しましょう。
ストレスが多い
ストレスはさまざまな病気の原因となる可能性があり、緑内障にとっても良くありません。
ストレスによって自律神経のバランスが乱れ、目への血流が悪化すると視神経が障害されてしまいます。
また、過剰なストレスによって睡眠不足になると、体内の活性酸素が過剰に発生して酸化ストレスが増加して目の組織を傷つけてしまうこともあります。
ストレスの原因を減らしたり、リラックスして睡眠不足を解消したりできるように、工夫してみましょう。
目に負担がかかる習慣
目に負担がかかる習慣は、直接緑内障の原因になるわけではありませんが、眼精疲労が蓄積される、近視が進行するなどの理由から、緑内障になりやすくなる可能性があります。
スマートフォンやゲーム、パソコンなどの電子画面を長時間見続けるのは、目の負担になるため避けましょう。
また、デスクワークや読書、暗い場所での作業などは下を向く姿勢にもなるため首や目、脳への血流が悪くなります。
目を使うときは、遠くを眺める、立ち上がって伸びをするなど、こまめに休憩をとって目を休める時間を意識的に作ってみてください。
眼圧が上がりやすい習慣
眼圧が上がりやすい生活習慣は、緑内障のリスクファクターとして挙げられます。
高い枕で寝ていると、首へ負担がかかったり、頭の位置が高くなり血流が滞ったりして、目への栄養や酸素が不足して眼圧が上昇する可能性があるため、低い枕に変えてみましょう。
また、うつ伏せ寝は下になっている方の眼球が圧迫されて、眼圧が上がりやすくなってしまいます。
視神経への負担を避けるため、なるべく仰向けに寝るように意識すると良いでしょう。
水分の摂りすぎ
水分を一気に摂りすぎると、眼圧が上昇しやすくなります。
夏場の暑い時期に大量の水分を一気に摂る、アルコールの一気飲みなども危険です。
水分補給は大切ですが、少量ずつ複数回に分けて飲むようにしましょう。
運動不足
運動不足は血流と深く関係していて、緑内障の直接の原因ではありませんが、リスクファクターのひとつとして挙げられます。
日常的に運動する習慣がない方は、血流が低下して視神経が障害される可能性があるのです。
また、運動不足により肥満や高血圧、さまざまな生活習慣病につながると、目だけでなく全身の健康状態にも影響します。
ウォーキングや軽いジョギングなど、続けやすい運動を心がけましょう。
ただし、筋トレや短距離走など力を入れて息を止める瞬間がある運動は、急激な心拍数の上昇により眼圧が上がりやすく、逆効果になりかねないため注意が必要です。
緑内障のリスクファクター|他の疾患

緑内障のリスクファクターとして、他の疾患も多く挙げられます。
目に関する疾患では、ぶどう膜炎や外傷は続発緑内障の原因です。
他にも、緑内障になりやすい全身の疾患について、詳しく解説します。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、緑内障を引き起こす原因となります。
糖尿病の進行により目に合併症が起こると目への血流が滞り、酸素不足を補うために新しい血管(新生血管)を作ることを糖尿病網膜症と呼びます。
新生血管のできる位置により隅角を塞いでしまったり、脆い新生血管が目の中で出血したりする恐れがあり、糖尿病網膜症から緑内障を発症すると、新生血管緑内障になるのです。
糖尿病を患っている方は、定期的な眼科検診で網膜の状態を確認し、合併症の前兆を見逃さないことが重要です。
睡眠時無呼吸症候群
いびきが大きい、睡眠時に呼吸が止まっていると指摘される方は、睡眠時無呼吸症候群かもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、寝ている間に呼吸が止まったり減ったりする病気です。
呼吸が止まるとその間は脳や目へ酸素が供給されない低酸素状態になり、血流への悪影響や眼圧が上がりやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群は自分で気づくことが難しく、緑内障だけでなく、心臓や脳への負担など他の病気を引き起こす可能性があるため、早めに診断を受けて治療を始めましょう。
高血圧・低血圧
極端な高血圧や低血圧は、血流に影響を与えて視神経にダメージを与えるリスクがあります。
高血圧が目以外の全身の健康に関わるのは一般的に知られていますが、極端な低血圧も目に必要な栄養や酸素が届かなくなる可能性があるため注意が必要です。
また、薬で急激に血圧を下げた場合も、目に影響が出ることがあります。
食事や運動、適切な治療で血圧をコントロールするのは、目にとっても大切だと覚えておきましょう。
片頭痛
片頭痛は血管が収縮して血液の循環が悪くなるため、頭が痛くなる症状が出ます。
血液循環が悪くなると視神経が障害されて、緑内障のなかでも正常眼圧緑内障を発症する可能性が高まります。
正常眼圧緑内障は初期には自覚症状がほとんどなく、発症しても気づきにくく、時間をかけてゆっくり進行していくため、気づいたときは視野の欠けが広がっていることもあるのです。
片頭痛は体質だからと治療をしていない方も多いですが、もしかしたら緑内障や他の病気が隠れているかもしれません。
医師とよく相談して、必要な治療や検査を受けることを検討してみましょう。
緑内障のリスクファクター|その他の要因
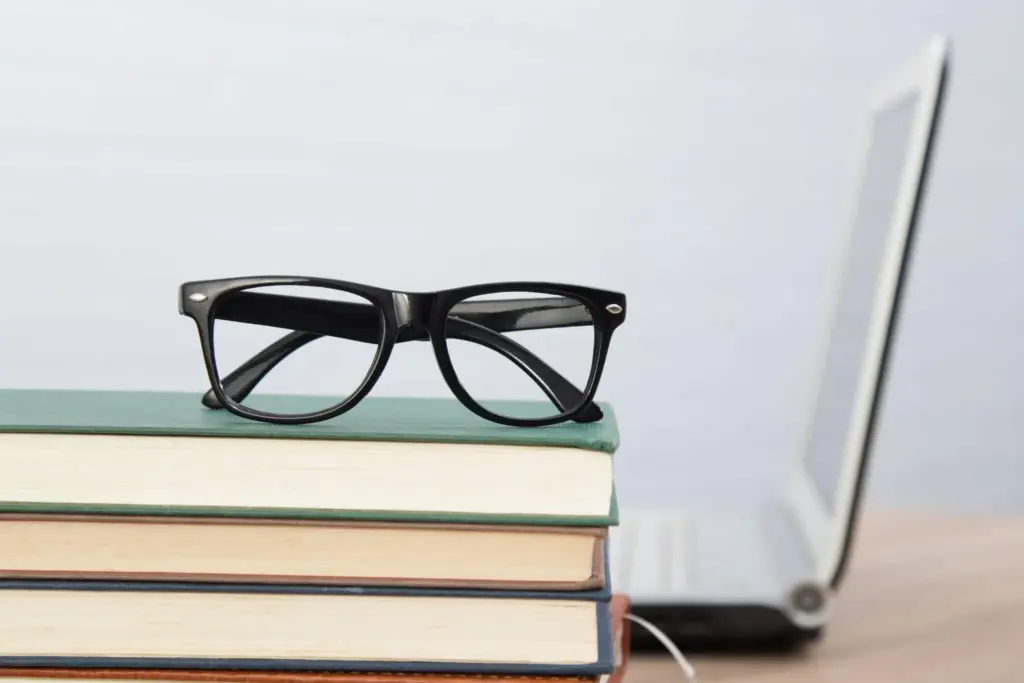
生活習慣や他の疾患以外の緑内障のリスクファクターは、以下の通りです。
強い近視がある
強度近視と呼ばれる-6.0D以上の方は、緑内障になるリスクが高くなる傾向があります。
強い近視があると、通常は球形の眼球が前後に伸びていて、視神経や血管も引き伸ばされてしまうことがあり、脆くなってダメージを受けやすくなります。
また、網膜や目全体にも負担がかかるため、強い近視はさまざまな目の病気の原因になりかねません。
定期的な眼科検診を受けて、目の状態をチェックすることが重要です。
血縁者に緑内障の方がいる(遺伝)
遺伝的要素も、緑内障のリスクファクターとして挙げられます。
近い血縁者に緑内障の方がいると、いない方と比較すると緑内障になる可能性が高い傾向があります。
ただし、眼圧の調整機能や視神経の強さなどが遺伝と関係していると考えられていますが、はっきりとはわかっていません。
また、小児緑内障の一部は遺伝性のものである可能性があります。
家族や親戚の方に緑内障の方がいる場合は、意識して定期的に眼科検診を受けましょう。
年齢(40歳以上)
緑内障は40歳以上になると発症率が上がり20人に1人、70歳以上は10人に1人が緑内障を患っているとされています。
(参照:「日本緑内障学会多治見緑内障疫学調査(通称:多治見スタディ)報告」日本緑内障学会)
これは有病率であり、緑内障の診断や治療を受けている人数ではありません。
加齢による目の組織の老化や機能低下により、房水の循環が滞り眼圧が上がりやすくなることもあります。
また、視神経が弱まり外部からの影響を受けやすくなるため、少しの眼圧の変化がダメージにつながる可能性も高まります。
緑内障は初期症状に気づかない方も多く、もともと視力が良いと眼科へ行く機会も少ないかもしれません。
40歳を機に定期的な眼科検診を受けることを心がけて、見え方の変化を観察するように心がけましょう。
薬の影響(ステロイドホルモン剤の内服や吸入)
ステロイドホルモン剤の長期間の使用は、緑内障のリスクファクターのひとつです。
アトピー性皮膚炎の治療でステロイド剤の内服や軟膏使用を長期間続けていたり、ぶどう膜炎やアレルギー性結膜炎などでステロイド点眼薬をしていたりすると、リスクが高まります。
ステロイドによる緑内障は続発緑内障に分類され、ステロイド薬の使用を中止すると眼圧が下がることもあります。
ただし、ステロイドを使用している疾患が悪化する恐れもあるため、自己判断で中止するのは避けて、医師の指示に従いましょう。
緑内障と診断されたらどうする?

緑内障により視野欠損や視力低下が起こった場合、治療で見え方を改善することは難しいため、早期発見・早期治療で現在見えている範囲を維持して、進行させないようにすることが重要です。
ここでは、緑内障と診断されたらどうするか、心がけてほしいことを解説します。
自分の緑内障タイプを知る
緑内障にはさまざまなタイプがありますが、自分がどのタイプの緑内障なのかを把握しておきましょう。
特に、閉塞隅角緑内障の方は隅角が突然閉じて急性緑内障発作が起こる可能性があるため、注意が必要です。
急性緑内障発作は、激しい目の痛みや頭痛、吐き気、嘔吐、目のかすみなどを伴い、放置すると数時間~数日で視力を失うこともあるため、すぐに適切な処置を行う必要があります。
緑内障以外の目や全身の病気治療をしている方は、内服薬の処方や注射の際に緑内障の申告が必要になる場合があり、タイプを知っておく必要があります。
ステロイド剤は緑内障の分類に関わらず、眼圧を上昇させる可能性があるため、使用するかは医師の指示に従いましょう。
また、閉塞隅角緑内障の方は、抗コリン薬は禁忌となります。
抗コリン薬により瞳孔が広がり、隅角の狭まりが進行してしまうからです。
一部の風邪薬や抗ヒスタミン剤などに含まれているため、安易に市販薬を飲むのは避けて、医師に相談して成分を確認しましょう。
今の視力を維持するための治療
緑内障の治療は、今の視力を維持するために行います。
点眼薬、内服薬、手術などで、眼圧を下げて緑内障の進行を抑制するのです。
日本人に多い原発開放隅角緑内障の治療は、点眼を続けるのが緑内障の悪化を防ぐカギとなります。
視力や視野を回復できるわけではありませんが、治療の開始が早ければ早いほど、見える範囲を保つことが可能となります。
通院を続ける
緑内障は初期症状がほとんどなく、見え方に異常を感じていない方も少なくありません。
自覚がないと治療に対して消極的な方も多く、途中で治療をやめてしまうケースもあります。
すると徐々に症状が進行して、気づいた時には視野が広く欠けてしまう方も珍しくありません。
緑内障の診断を受けると心配や不安が先にきてしまうかもしれませんが、早く発見できればそれだけ視力や視野を保てる可能性が高まります。
無理なく通院を続けて治療を継続できるように、医師とよく相談して治療計画を立てましょう。
日常生活を普通に過ごす
緑内障の診断を受けて、急に何かを我慢したり、気をつけたりする必要はありません。
読書や運動などの趣味は緑内障の進行には影響はほとんどなく、今まで通りに行えます。
目を使わないように趣味の読書をやめる、運動を制限するなど日常生活を大きく変えることは、逆にストレスになってしまうかもしれません。
一方、喫煙や過度の飲酒、食生活の乱れなど、明らかに健康に影響を与えることは改善した方が良いでしょう。
緑内障と診断されて気をつけることは、点眼治療を続ける、医師の指示通りに通院をするのが重要です。
まとめ
緑内障になりやすい条件は、ひとつではありません。
複数の要因が重なり、リスクが高まると考えられています。
原因がはっきりわかっていないため、リスクファクターを減らし、注意して観察していく必要があります。
緑内障は早期発見・早期治療が重要な病気です。
定期的な眼科検診を受けて、目の状態や見え方のチェックをして、今ある視力を大切に過ごしましょう。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、超広角眼底カメラによる散瞳不要の眼底検査を含む、緑内障の早期発見を目指した検査を実施しております。
患者さんお一人おひとりの症状やライフスタイルに合わせて、適切な治療をご提案させていただきます。
緑内障になりやすいのではと不安な方、眼科検診を受けたい方は、ぜひお気軽に『大阪鶴見まつやま眼科』へご相談ください。