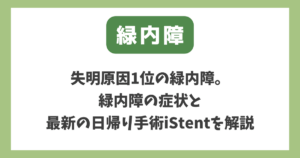緑内障は初期症状に気づきにくく、徐々に視野が欠けたり、視力が低下したりして、進行すると失明することがある病気です。
しかし、症状について知っていれば、早いうちに治療を受けて病気の進行を防げる可能性が高まります。
緑内障は、早期発見・早期治療が重要です。
この記事では、進行度別の緑内障の症状や、セルフチェックの方法、治療について詳しく解説します。
緑内障の症状や早期発見のための方法を知りたい方は、ぜひ参考にして下さい。
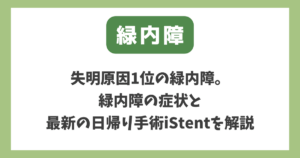
緑内障とは

緑内障とは、眼圧の上昇や他のなんらかの原因により視神経が障害され、視野や視力に悪影響が出る目の病気です。
治療が遅れたり、放置したりすると、失明に至ることもあります。
日本の視覚障害の原因疾患第1位となっていて、40%以上を占めており、40歳以上の20人に1人が患っているとされています。
(参照:岡山大学)
はっきりした原因はわかっていないため、「これをすれば予防できる」というものはないのが現状です。
障害された視神経は元に戻すことができず、失った視野を回復する治療もありません。
ただし、緑内障は適切な治療を行えば進行を防ぐことができ、今見えている視野や視力を維持できるのです。
そのため、40歳を過ぎたら定期的な眼科検診を受けて、早期発見・早期治療をすることが重要です。
緑内障の主な症状

緑内障を患うと、数年〜数十年かけて以下のような症状が進行します。
ここでは緑内障の主な症状について、詳しく解説します。
視野欠損
緑内障の症状で一般的に知られているものが、視野欠損です。
視野の一部分が欠けて見えている状態で、小さな点のようなものから始まり、徐々に点が大きくなり範囲が広くなっていきます。
左右どちらかの視野が欠け始めても、見える方の目や脳で補っているため自覚するのは難しく、気づいたときにはかなり視野が欠けてしまっていることも珍しくありません。
視野欠損は目頭側や上下などの端から始まるケースが多く、意識して見え方をチェックしなければ見逃してしまいます。
また、緑内障の症状はゆっくり時間をかけて進行していくため、見え方の変化に気づきにくいのも特徴です。
視野狭窄
視野狭窄とは、見える範囲が狭くなっていく状態です。
視線を動かさずに見えていた端や上下から徐々に見えなくなり、中期~後期にかけて中心部分だけしか見えなくなります。
頭や首ごと動かさないと足元や横が見えなくなる状態まで進行すると、死角が増えて日常生活にも支障をきたしてしまいます。
後期になり中心部分も見えなくなったら、失明する可能性が高いでしょう。
視力低下
視野欠損や視野狭窄が進むと、視力自体が低下していきます。
ぼやけて見えたり、夜や暗い場所でものが見えづらくなったりするのも視力低下の症状です。
視力低下は長い時間をかけて進むため、変化に気づきにくいかもしれません。
健康診断や眼科検診で、定期的に視力検査を受けて、視力の変化を把握しておくのが重要です。
急性緑内障発作の症状に注意

代表的な緑内障の症状の他に、注意しなければならないのが急性緑内障発作です。
緑内障は大きく以下の4つに分類されます。
- 開放隅角緑内障
- 閉塞隅角緑内障
- 続発緑内障
- 小児緑内障
このうち、閉塞隅角緑内障で起こるのが、急性緑内障発作です。
急激に眼圧が上昇(40mmHg~60mmHgほど)して激しい目の痛みや頭痛、吐き気、嘔吐、目のかすみ、充血などが突然現れます。
急性緑内障発作は、眼球を満たす水分である房水の排出を行う隅角が、急に閉じたり狭まったりして起こり、放置すると数時間~数日で失明する恐れがあります。
早急に眼圧を下げる治療が必要なため、すぐに眼科を受診して適切な処置を受けてください。
進行度別|緑内障の症状
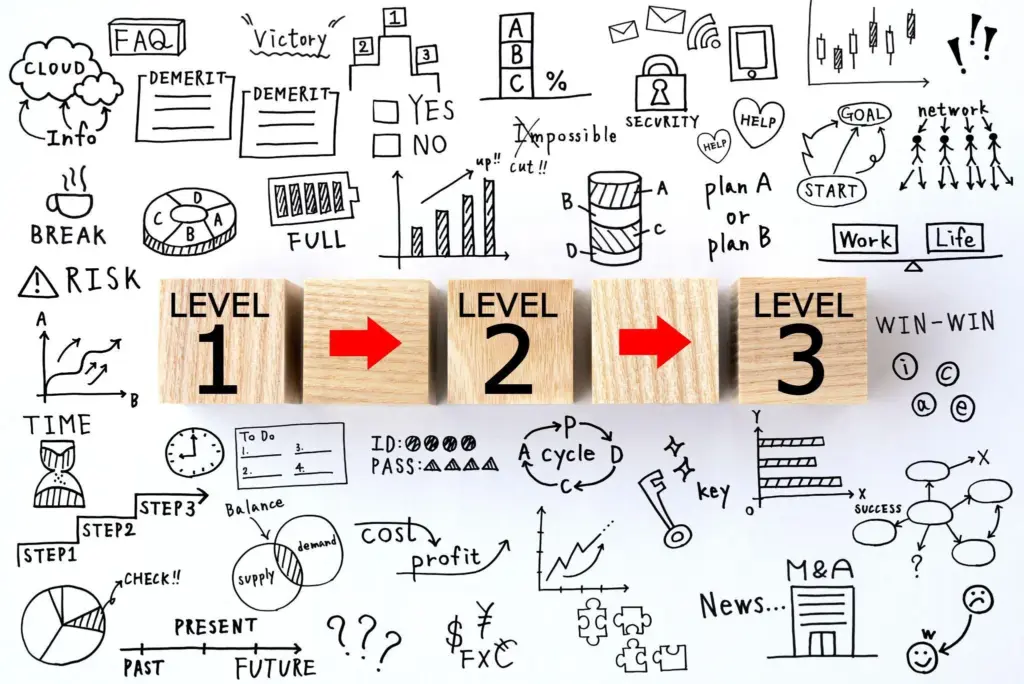
緑内障で最も多いのが、眼圧が正常範囲内(10mmHg~20mmHg)で発症する正常眼圧緑内障です。
その他の種類の緑内障でも慢性が多く、症状はゆっくり時間をかけて進行していきます。
ここでは、進行度別の緑内障の症状について、見え方や症状の出方を詳しく解説します。
初期段階
緑内障の初期段階では、自覚症状はほとんどありません。
軽度の視野障害がある方もいますが、自分で見え方に変化を感じることはあまりないでしょう。
どちらかの目に視野欠損やぼやけて見える箇所があったとしても、左右それぞれの目でお互いに補い合ってものを見ているため、意識して片目ずつ見ないと気づけません。
この段階で眼科検診を受けると、視野検査や眼圧検査では緑内障の兆候が見られないかもしれませんが、OCT(光干渉断層計)検査を行うと初期の緑内障を発見できる可能性が高いです。
眼科検診を受けるときは、OCT検査に対応しているクリニックを選ぶのをおすすめします。
中期段階
中期の段階では、視野欠損が少しずつ進んでいますが、まだ自覚がない方も少なくありません。
欠けた部分が広がっても両目が同じように進行しているわけではなく、見える方の目で補える範囲の場合は気づきにくいのです。
高齢の方は他にも目の病気があると、見え方に違和感があっても緑内障だと思い当たらないこともあります。
上側の視野が欠けていても、上まぶたが下がってきていて見えていないと思い込んでいる場合もあります。
40歳以上になったら、定期的な眼科検診を受けたり、片目ずつセルフチェックをしたりして、緑内障の症状がないか確認しましょう。
後期段階
後期段階になると、視野欠損や視野狭窄、視力低下などの症状を自覚する方が多くなります。
視野欠損が目頭側や上下の端から中心に向かって広がっていき、視力の低下も伴います。
足元が見えずに躓くことが多くなる、文章がまっすぐ書けなくなる、階段を踏み外すなどの日常生活の支障が起こり、緑内障に気づくケースが多いです。
緑内障は進行が遅く、治療の成果が実感しにくいことから、治療を途中でやめてしまう方も少なくありません。
視神経が障害されて欠けた視野は回復できず、視力を失わないためにはすぐに適切な治療を開始するのが重要です。
緑内障のセルフチェック
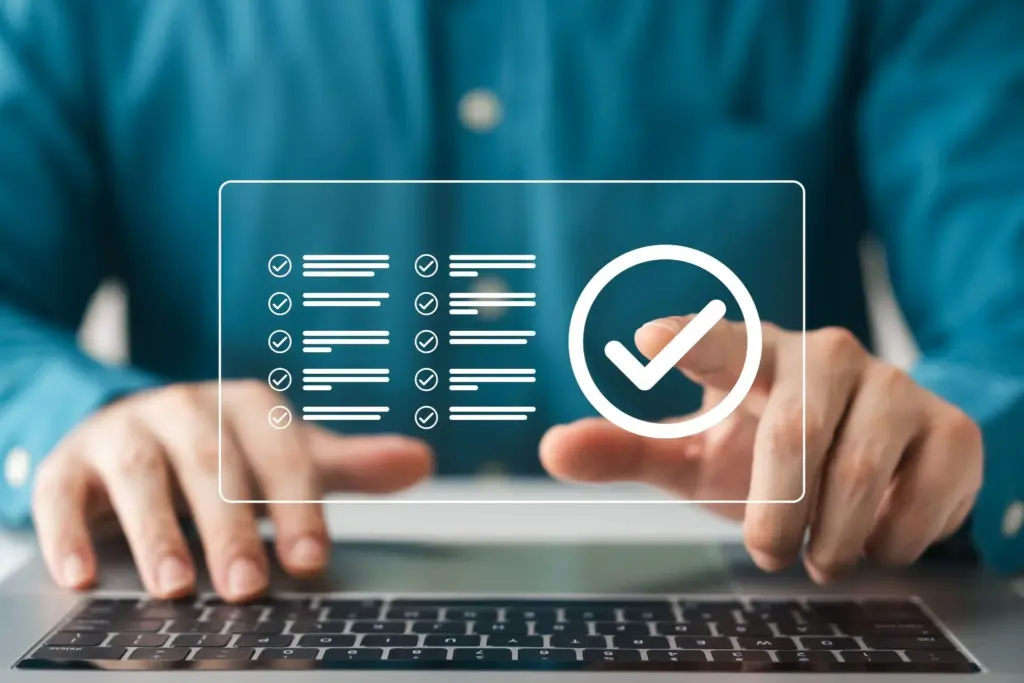
緑内障の早期発見をするためには眼科検診を受けるのが大切ですが、忙しかったり自覚症状がないのに病院に行くのが億劫だったりして、ハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
クリニックまで出かけるのが難しいと感じる場合は、簡単なセルフチェックで緑内障の兆候があるかを確認できます。
ただし、セルフチェックはあくまで緑内障を早期発見する手助けをするのが目的となります。
異常が見つかった場合は、すぐに眼科を受診して、治療を開始することが必要です。
セルフチェックの必要性
定期的にセルフチェックをすると、緑内障の症状のチェックとともに目の健康を意識することにもなります。
目の異常や視力の変化を確認することで、「緑内障かもしれない」と不安になる気持ちを軽減して、早いうちに治療を開始することができます。
また、セルフチェックの記録を取っていれば、少しの変化に気づきやすくなり、緑内障の早期発見につながるでしょう。
セルフチェックはいつ行う?
セルフチェックはタイミングを決めて行うと効果的です。
例えば、視力が安定している朝に毎回同じ場所を片目ずつ見てみる、月に1度家族で協力しながら視力チェックする時間を作るなど、日常生活に取り入れるのをおすすめします。
毎日、毎月などやりやすい時間を決めて、同じタイミングで定期的に行うのがポイントです。
自宅でできる緑内障チェック方法
特別な道具がなくても、簡単に続けられるセルフチェック方法をご紹介します。
- 片目ずつ遠くと近くを交互に見てみる
- 本や新聞などの文字の読みにくさがないか
- カレンダーやポスターの細かい文字がぼやけて見えないか
これらをなるべく同じ条件で定期的に行うと、変化がわかりやすいでしょう。
意識していないと、日常生活の中で片目でものを見ることはないため、片目ずつチェックするのが重要です。
視力の変化は老眼や近眼の進行によってもありますが、左右差があると感じた場合は眼科を受診して詳しく検査しましょう。
アムスラーグリッド
アムスラーグリッドは、方眼紙のシートを利用して行う視野欠損をチェックする方法です。
パソコンの画面上やインターネットでダウンロードして印刷して、セルフチェックに取り入れてみましょう。
- 明るい部屋で行い、メガネやコンタクトを装着する
- アムスラーグリッドと顔の距離は30cm離す
- 片目を閉じて、中央の点を見つめる
- 方眼の線が歪んでいないか、欠けている場所がないかを確認
- もう片方の目も同様に行う
見え方に異常がある場合は、すぐに眼科を受診して、緑内障の詳しい検査を受けましょう。
パソコンでできるセルフチェック
VIATRIS社のホームページでは、パソコンでセルフチェックができます。
- 簡易版ノイズフィールドチェック
- 「視野の欠け」チェック
- 簡易版FDTチェック
3種類のチェックにより、ちらつきや視野の欠けなどを確認することができます。
スマートフォンでは利用できませんが、パソコンがあればいつでもチェックができて、定期的に見え方を確認するために有効です。
ただし、緑内障の診断をするものではなく、見え方の異常がないかを確認するために活用するツールです。
緑内障の治療のためには眼科を受診して検査を行い、医師の診断を受けてください。
緑内障の治療

緑内障と診断されたら、なるべく早いうちに眼圧を下げる治療を開始します。
正常眼圧緑内障でも、眼圧を下げる治療が有効です。
今見えている視野や視力を維持して、緑内障の進行を抑える治療です。
他の疾患が原因である続発緑内障の場合は、原因となった病気の治療を行います。
自覚症状があまりない時期だと、見え方が変わらないからと治療をやめてしまう方が多く、問題になっています。
視野欠損や視力低下を自覚してからでは、元に戻すことはできません。
緑内障の治療は継続して行うのが重要だと、覚えておきましょう。
点眼薬
緑内障の治療は、点眼薬が多く用いられます。
眼圧を下げる作用のある点眼薬で、適正な眼圧を保つ治療です。
点眼薬には複数の種類があり、房水に作用するものや血流改善を促すものなど、効果はさまざまです。
症状や進行度、求められる眼圧などの要素を鑑みて、複数を組み合わせて処方されることもあります。
点眼薬は毎日自分で行う治療であり、継続することが重要です。
途中でやめてしまったり、点眼を忘れてしまったりすることがないように心がけましょう。
内服薬
緑内障の治療では、必要に応じて内服薬を使用することもあります。
しかし、長期的な使用は全身の副作用が現れる場合があり、長く使用するのは推奨されていません。
内服薬の服用ができるかどうかは、医師とよく相談してください。
レーザー治療
レーザー治療はいくつかの種類があり、緑内障のタイプや症状により方法を選択します。
レーザー虹彩切開術は、急性緑内障発作や多くの閉塞隅角緑内障に有効な、虹彩に小さな穴を開けて房水が流れるための道を新しく作る方法です。
レーザー線維柱帯形成術では、線維柱帯(房水の出口)にレーザーを照射して目詰まりを解消する方法で、一部の開放隅角緑内障に対して行われます。
レーザー治療は短時間(約5~10分)で済み、日帰り可能なクリニックもあるため問い合わせてみましょう。
手術
薬物療法やレーザー治療で眼圧が下がりきらない場合には、手術を行うこともあります。
房水流出路再建術として、線維柱帯を切開して房水が流れる量を増やす線維柱帯切開術や、白内障手術併用眼内ドレーンが挙げられます。
濾過(ろか)手術としては、開放隅角緑内障を含めた多くの緑内障に有効とされる、線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)や、眼内にチューブやプレートの人工物(インプラント)を挿入して房水の流出を促すチューブシャント手術などがあります。
手術の術式は、緑内障の病型や症状、全身状態、社会的背景などさまざまな点を考慮して、医師とよく相談したうえで検討しましょう。
まとめ
緑内障は初期症状がほとんどなく、自覚するのが難しい病気です。
視野欠損や視野狭窄、視力低下など、見え方に異常があると感じたときには、中期~後期まで進行してしまっている可能性もあります。
緑内障は早期発見・早期治療をするためにも、定期的な眼科検診やセルフチェックを継続して行うことが重要です。
片目ずつ見え方をチェックしてみる、パソコンでできるセルフチェックを毎月の習慣にするなどを、意識して行いましょう。
治療をせずに放置すると失明の可能性もあるため、毎日の点眼と通院を継続し、今ある視力を大切にしましょう。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、患者さんの目の健康を守るため、お一人おひとりのライフスタイルに合わせて適切な治療法をご提案させていただきます。
低侵襲緑内障手術(MIGS)の日帰り手術にも対応しています。
緑内障かもしれないと不安な方や、負担の少ない手術を受けたい方は、『大阪鶴見まつやま眼科』へお気軽にご相談ください。