オルソケラトロジーは就寝中に特殊なコンタクトレンズを装用し、角膜の形状を変化させて近視の視力矯正を行う治療法です。
日中はレンズを外しても改善した視力のまま快適に過ごせますが、角膜の形状が変わると聞くと、何かの失敗をきっかけに失明するのでは?と心配になる人もいるでしょう。
この記事では、オルソケラトロジーの失明のリスクや原因、失明を避ける対策などを紹介します。
オルソケラトロジー自体は安全性が世界各国で認められている治療法であるため、正しい認識を持って適切な取り扱いができるよう、ぜひ参考にしてください。

オルソケラトロジーで失明する可能性は?

実際、オルソケラトロジーで失明する可能性はあるのでしょうか?
まず初めに、オルソケラトロジーの安全性や失明の可能性について紹介します。
失明の可能性はほとんどない
オルソケラトロジーのレンズを正しく使用していれば、失明する可能性はほとんどありません。
オルソケラトロジーはアメリカで30年以上研究されてきた矯正法で、以下の機関によって安全性や有効性が認められ認可・認証されています。
- FDA(米国連邦食品医薬品局)
- FAA(米国連邦航空局)
- CEマーク(欧州連合地域)
- 厚生労働省
厚生労働省では2009年に認可された、比較的新しい治療方法です。
失明の可能性がゼロではない理由
オルソケラトロジーに失明の可能性がゼロではない理由は、正しい使用法や使用上の義務が守られていない場合があるためです。
オルソケラトロジーはそのほとんどが自宅で行う近視矯正法のため、気軽にできるという意識から、取り扱いが疎かになりがちな点が否めません。
特にレンズケアがしっかり行われない場合、合併症のリスクがあるため、注意が必要です。
正しい方法でレンズケアを行い清潔な状態を保ち、定期検診を受け、リスクを低減しましょう。
オルソケラトロジーで失明しないために

オルソケラトロジーで失明しないために、使用する患者側にできることがあります。
オルソケラトロジーのレンズの正しい管理方法と、定期的に行う検診について紹介します。
レンズの正しい管理
オルソケラトロジーに限らず、ハードコンタクトレンズは洗浄が不十分だったりレンズケースの清潔が保たれていないと、角膜感染症や角膜炎などの合併症を引き起こす場合があります。
特にオルソケラトロジーのレンズはリバースカーブと呼ばれる溝のようなカーブが輪状に走るという、汚れが溜まりやすい特殊な形をしています。
目の重い障害につながることのないよう、また、目的となる近視矯正効果が期待通りに得られるよう、適切な管理が重要です。
オルソケラトロジーのレンズは、眼科で提供されたケア用品を使用してしっかりケアしましょう。
定期的な検診
オルソケラトロジーは定期検診を必ず受けなければいけません。
眼科によって違いはありますが、初年度は一例として装用から1週間後・1か月後・3か月後の検診がまず必要で、その後は3~4か月毎に定期検診を受けることになります。
オルソケラトロジーの定期検診では以下のようなことが行われます。
- 視力検査(度数が変わればレンズを作り直す必要がある)
- 就寝時のレンズ位置の確認
- 眼科の診察(目に傷がないか)
- レンズの傷や汚れなどの状態の確認(新しいレンズへの交換時を確認)
オルソケラトロジーのレンズは治療を終えたりやめたりする際には返却する義務があるレンタルの医療機器のため、定期検診ではレンズの状態確認や維持管理も行われます。
定期検診はオルソケラトロジーを続けるための義務のため、医師の指示に従いきちんと受けましょう。
オルソケラトロジーのレンズの管理方法
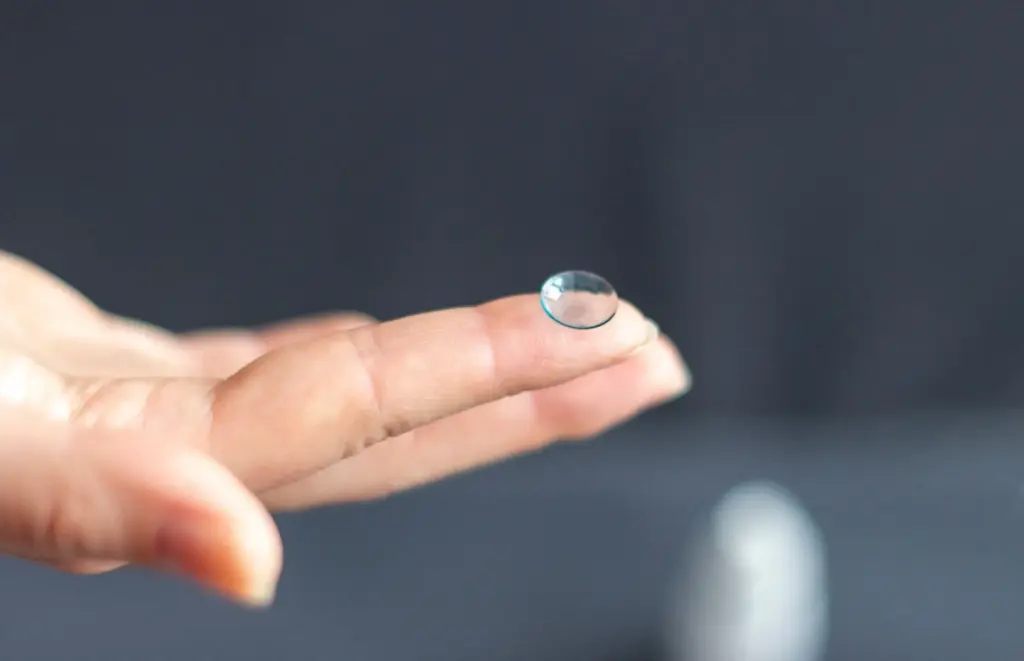
オルソケラトロジーのレンズの洗浄方法や取り扱い方など、管理方法を紹介します。
レンズは正しく取り扱わないと、破損や歪みが発生すると角膜に傷をつけたり、ケア不足で感染症を引き起こしたりなど、さまざまなトラブルに発展する危険性があります。
正しく扱うことでレンズの寿命も延ばせるため、大切にケアし管理しましょう。
レンズを取り扱うときの手に気をつける
レンズを取り扱うときは、レンズに触れる手に気をつけましょう。
オルソケラトロジーのレンズを着け外しや洗浄をする前など、レンズに触れる際は以下のポイントを確認してください。
- 目の状態を確認……充血や目やにがないか確認する
- 爪を切る……長い爪はレンズを傷つけ、そこに汚れが溜まったり目を傷つけたりする
- 石鹸で手を洗う……手の汚れは細菌汚染の原因となる。よくすすぐこと
- 手を洗ったあとは清潔なタオルで水気を拭き取る……レンズに水滴や汚れが残るため
就寝前の装用時や起床後の取り外し時など、こまめに洗いましょう。
レンズの取り扱い方法
レンズはいい加減に扱うと傷が付いたり菌がついたりして、結果的に目を傷つけることにつながる危険性があります。
レンズの取り扱いについては、以下のことに注意しましょう。
- レンズを利き手の人差し指の先の上に乗せ、傷・変形・変色がないかよく確認する
- レンズを持つときは、人差し指や中指・親指などで軽く持つ
- ホルダーにはゆっくり出し入れする(必ず専用のケースを使用する)
- レンズケースは常に清潔に。装用中はよく乾燥させる
- レンズを落としたときは、人差し指と親指の腹で、レンズの端を軽くつまむ
特にレンズケースは3ヶ月に1回のペースで新しいものと交換し、定期検診の際もケースに入れて持参します。
ハードコンタクトレンズは無理な力を加えると割れてしまうため、優しく扱いましょう。
レンズを洗浄する
オルソケラトロジーのレンズケアの中でも、洗浄は特にしっかり行って欲しいケアです。
オルソケラトロジーのレンズの洗浄は、装用の前と外した後の両方のタイミングに、以下の順番で行います。
- 手のひらに、または人差し指と中指の間に、内側を上にしてレンズをのせる
- 手のひらにのせた場合は手のひらを丸めて安定させる
専用の洗浄液をたらし、人差し指か濡れた綿棒で円を描くように20秒ほどこする - 水かぬるま湯で洗い流す
こすり洗いをするとき、レンズがゆがむ可能性があるため、親指と人差し指で挟んで洗ってはいけません。
また、万が一落としてしまった場合に流してしまわないよう、排水口には流出防止マットの使用をおすすめします。
また、2週間に1度は専用のタンパク質除去剤で浸け置きしましょう。
オルソケラトロジーの定期検診スケジュール
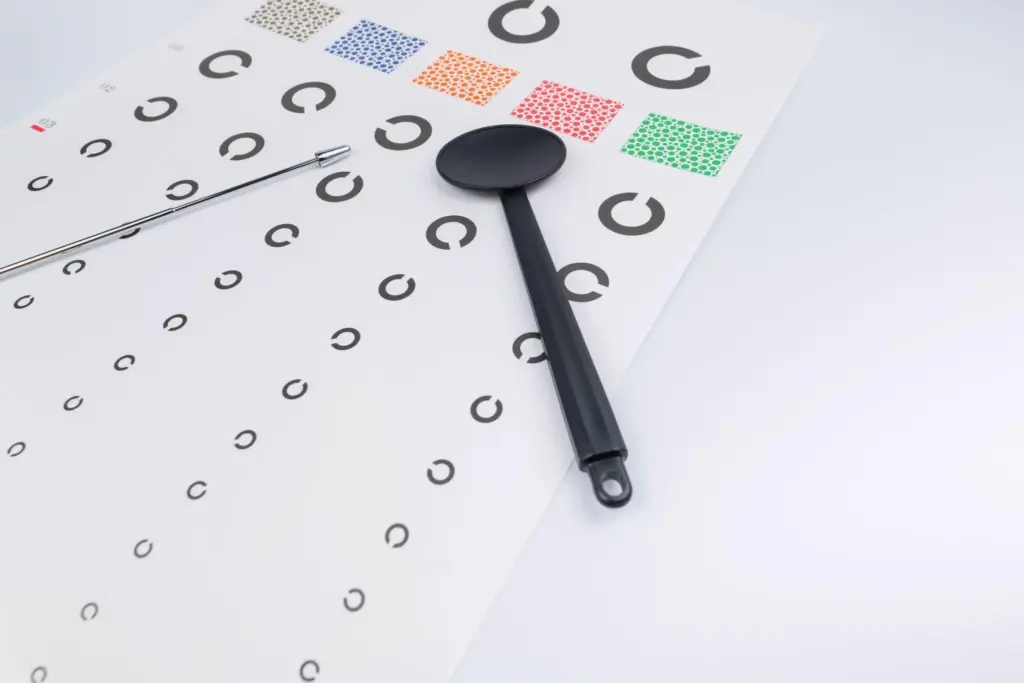
オルソケラトロジーに慣れるまでの間、定期検診を近い間隔で受けて、様子を確認しながら矯正を進めていきます。
患者さんに合ったレンズを作成し、治療を開始するための大切なプロセスである、オルソケラトロジーの初年度の定期検診スケジュールを紹介します。
1.適応検査
まずはオルソケラトロジーが適応となるかどうかの検査を行います。
以下は検査内容の一部です。
- 近視の程度(強度の場合はオルソケラトロジーの適応ではないため)
- 疾患の有無
- 角膜の状態
- 眼底検査
- 屈折値検査
- 涙液の検査 など
適応検査で適応と判断され、患者さんにも継続の意思がある場合、患者さんの目に合うレンズをオーダーします。
トライアルレンズを当日1時間ほど装用してみる、トライアルレンズの貸出をして1週間ほど試してみるなど(有料/約33,000円)、眼科によって治療開始までの流れには違いがあります。
2.治療(装用)開始
適応検査を終えてレンズを選択・作成したら、いよいよ装用を開始します。
目に合わせた専用レンズを受け取り、装用練習・レンズの取り扱いやケア方法の説明を受け、初期費用等を支払い、同意書を提出します。
3.1週間後
次の受診(検診)は1週間後です。この辺りはクリニックによって違いがあります。
オルソケラトロジーの視力矯正の効果は装用開始翌日から感じられることが多いですが、最初のうちは夕方頃に少し視力が落ちることもあります。
オルソケラトロジーの矯正効果を実感するのは、裸眼で終日視力が持つようになるのは3日間程度、十分な視力を安定して得られるようになるのは1週間後辺りです。
5.1か月後→2か月後→3か月後、以降3~4か月ごと、または医師の指定した日
その後、次は1か月後→2か月後→3か月後、と少しずつ間隔を開けながら進み、順調にいけばその後は3~4か月に1回の定期検診となります。
定期検診を怠ると早期発見できる合併症を見つけられずに悪化させてしまうこともあるため、きちんと頻度を守って受けましょう。
オルソケラトロジーを行う期間

ここでは、オルソケラトロジーはどの程度の期間の治療が必要なのかを紹介します。
子どもは成長期の間
子どもの近視は子どもが成長している間は進行を続け、成長が止まると近視の進行も治まると考えられています。
子どもの角膜は柔らかく、オルソケラトロジーの効果が出やすい傾向があるため、近視の進行がゆるやかになっていく思春期以降(15~18歳)までは治療を継続するのが適切です。
しかし、近視が進行してしまいオルソケラトロジーの適応度数を超えてしまった場合は治療を中断することになります。
成長期の間に適応度数を超えてしまうことがないよう、早めの治療開始が大切です。
大人は個人の希望による
大人の場合はすでに近視が進行しており、オルソケラトロジーによる近視の進行抑制効果は期待できません。
そのため、日中に裸眼で活動したいという希望の程度によって、治療期間も変わるでしょう。
近視を根本的に解決したい場合は、レーシックやICLなどの選択肢を視野に入れる必要があります。
オルソケラトロジーを行っている間はリスク管理が必要
上で紹介したとおり、オルソケラトロジーを行っている間はレンズケアや定期検診など、合併症のリスクを避けるための管理が必要です。
しかし、3か月に1回の定期検診を受けていれば、医師がそのリスク管理を一緒に行ってくれるようなものです。
定期検診は、失明の原因となる合併症の早期発見のためにも非常に重要です。
オルソケラトロジーを安全に使用し続けるためにも、定期検診をしっかり受けましょう。
まとめ
オルソケラトロジーで失明する可能性がゼロではないと言われる理由は、レンズケアや定期検診などの義務がうまく果たせなかった際に起こる可能性があるためです。
逆を言えば、レンズケアと定期検診のどちらも医師の指示通り行えていれば、失明する可能性はほとんどないといえるでしょう。
大阪市鶴見区の『大阪鶴見まつやま眼科』では、オルソケラトロジーの豊富な処方実績があることに加え、小児眼科を得意とする視能訓練士が在籍しています。
オルソケラトロジーの効果をより引き出すことが期待できる体制で、患者さんのニーズにお答えします。
大阪鶴見でオルソケラトロジーを検討している人はぜひ、『大阪鶴見まつやま眼科』にお話をお聞かせください。
Web予約をお待ちしております。


