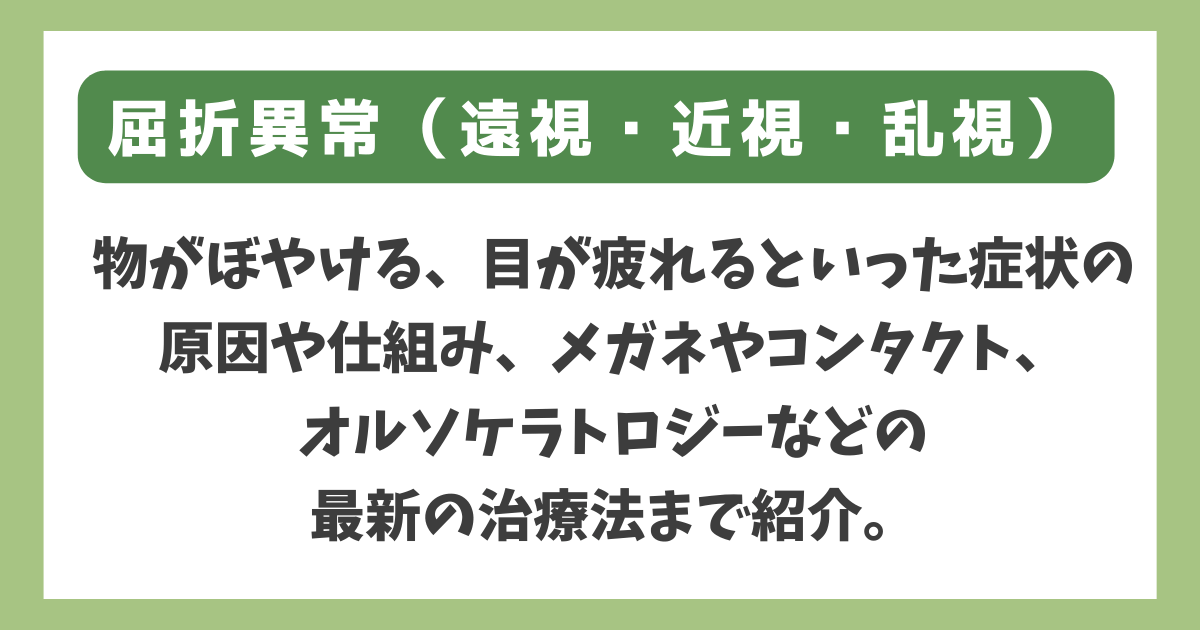「遠くの文字がぼやけて見える」
「手元のスマホは見えるのに、少し離れると見えにくい」
「パソコン作業をすると、夕方にはひどく疲れる」
「夜、信号の光がにじんで見える」
こうした「見え方」に関するお悩みは、年齢を問わず多くの方が抱えています。その不調の原因は、「屈折異常」かもしれません。屈折異常とは、目に入ってきた光が網膜の上で正しくピントを結ばない状態のことで、代表的なものに「近視」「遠視」「乱視」の3つがあります。
これらは単に「目が悪い」と一括りにされがちですが、それぞれ見え方の特徴や原因、そして適切な対処法が異なります。ご自身の目の状態を正しく理解することは、快適な毎日を送るための第一歩です。
この記事では、ご自身の見え方に疑問や不安を感じている患者さんに向けて、眼科専門医の立場から以下の内容を分かりやすく解説していきます。
- そもそも「見える」とはどういう仕組みか
- 「近視」「遠視」「乱視」それぞれの特徴・原因・症状
- 眼科で行われる精密な視力検査について
- メガネ、コンタクトから手術まで、様々な矯正・治療法
この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身やお子さんの目の状態を正しく理解し、どのような選択肢があるのかを知ることができます。見え方の「なぜ?」を解消し、クリアな視界を取り戻しましょう。
「目が見える」仕組みとは
屈折異常を理解するために、まず私たちの目がどのようにして「物を見ている」のかを知る必要があります。目はよくカメラに例えられます。
- 角膜と水晶体:カメラの「レンズ」の役割。外から入ってきた光を屈折させて曲げます。
- 網膜:カメラの「フィルム」や「イメージセンサー」の役割。レンズを通った光が像を結ぶスクリーンです。
物がはっきりと見える状態、すなわち「正視」とは、この「レンズ(角膜・水晶体)」が光をちょうどよく曲げ、その焦点がピッタリと「フィルム(網膜)」の上で合う状態を指します。この時、私たちは力を入れなくても楽に物を見ることができます。
「屈折異常」とは、このピントが網膜の前や後ろにずれてしまっている状態の総称です。
近視・遠視・乱視のメカニズムと症状
それでは、3つの代表的な屈折異常について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 近視
【どんな見え方?】
近くは見えるが、遠くがぼやけて見える状態です。日本人には最も多い屈折異常で、小学生から増え始めます。
【なぜ起こる?】
ピントが網膜の「手前」で合ってしまっている状態です。主な原因は2つあります。
- 軸性近視:眼球の奥行き(眼軸長)が正常より長すぎるため、網膜が後ろに下がり、ピントが手前にずれてしまいます。多くの場合、遺伝や成長期の生活環境が影響すると考えられています。
- 屈折性近視:角膜や水晶体の光を曲げる力が強すぎるために、ピントが手前にきてしまう状態です。
近年、子供の近視が世界的に増加しており、スマホやタブレットなどの近距離作業(近業)の増加や、屋外活動の減少が関係していると考えられています。
2. 遠視
【どんな見え方?】
「遠くがよく見える目」と誤解されがちですが、正しくは「遠くも近くも、ピントを合わせるために常に目の筋肉(毛様体筋)を頑張らせないと見えない目」です。ピントが網膜の「後ろ」で合ってしまうため、常に水晶体を厚くしてピントを前に持ってくる調節力を使っています。
【なぜ起こる?】
主な原因は、眼球の奥行き(眼軸長)が正常よりも短い「軸性遠視」です。
【症状】
若い頃は調節力が強いため、裸眼でも視力が良いことが多く、遠視に気づかない「隠れ遠視」のケースも少なくありません。しかし、常に目を頑張らせているため、以下のような症状が出やすくなります。
- 眼精疲労(目が疲れやすい、しょぼしょぼする)
- 頭痛や肩こり
- 集中力が続かない
特に注意が必要なのは、お子さんの遠視です。強い遠視を放置すると、視力の発達が妨げられる「弱視」や、目が内側に寄ってしまう「内斜視」の原因になることがあります。
3. 乱視
【どんな見え方?】
距離に関わらず、物が二重に見えたり、輪郭がにじんで見えたりする状態です。角膜や水晶体の歪みによって、ピントが1点に集まらず、複数にずれてしまうために起こります。
【なぜ起こる?】
多くは、角膜がラグビーボールのように縦横でカーブが異なる「正乱視」です。これにより、縦方向の線ははっきり見えるのに横方向の線はぼやける、といった症状が出ます。夜間に信号や対向車のライトがギラギラと眩しく見えるのも乱視の典型的な症状です。
また、目の病気(円錐角膜など)や怪我によって角膜の表面が不規則に歪む「不正乱視」もあります。これはメガネでの完全な矯正が難しく、ハードコンタクトレンズなどが必要になります。
当院で行う検査と診断
「視力が落ちたかな?」と感じた時、自己判断や雑貨店などで作製したメガネで済ませてしまうのは危険です。
大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、見えにくさの背景に病気が隠れていないかを含め、専門的な検査で正確な目の状態を診断します。
- オートレフケラトメータ検査:気球の絵などを見る、おなじみの機械です。目の屈折度数や乱視の強さ、角膜のカーブなどを客観的に測定します。
- 自覚的屈折検査:「赤と緑、どちらがはっきり見えますか?」「Cのマークの向きは?」といった質問をしながら、患者さん自身の「見え方」を確認し、最も快適に見える度数を精密に測定します。
- 視力検査:矯正した度数で、どのくらいまで見えているか(矯正視力)を確認します。
- 調節機能検査:特に子供の場合、目の緊張をほぐす目薬を使って、本来持っている遠視や近視の度数を正確に測ることが非常に重要です。
屈折異常の矯正と治療法
屈折異常は病気というより「目の個性」に近いものです。生活に不便を感じる場合は、以下のような方法で矯正します。
1. メガネ
最も安全で手軽な矯正方法です。使用するレンズの種類は屈折異常によって異なります。
- 近視:光を拡散させる「凹レンズ」で、手前にあるピントを網膜まで下げます。
- 遠視:光を集める「凸レンズ」で、後ろにあるピントを網膜まで前に出します。
- 乱視:一方向の光だけを屈折させる「円柱レンズ」で、ピントのズレを補正します。
2. コンタクトレンズ
角膜に直接乗せて視力を矯正します。広い視野が得られる、見た目が変わらない、スポーツに適しているなどのメリットがあります。一方で、衛生管理を怠ると重篤な眼障害を引き起こすリスクがあるため、正しい知識と定期的な眼科検診が不可欠です。
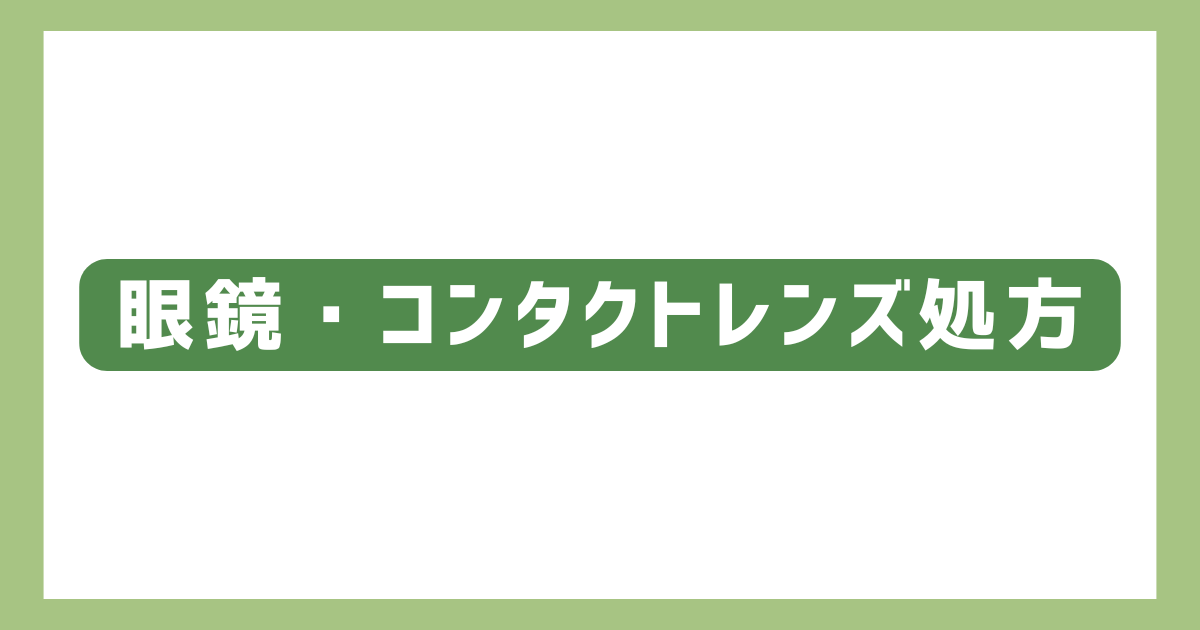
3. オルソケラトロジー
夜寝ている間に特殊なハードコンタクトレンズを装用し、角膜の形状を一時的に変化させて近視や乱視を矯正する方法です。日中は裸眼で生活できるため、スポーツをするお子さんなどに人気があります。また、子供の近視進行を抑制する効果が期待できる治療法として注目されています。自由診療となります。

4. 屈折矯正手術(当院では行っておりません)
成人し、視力が安定した方向けの選択肢です。裸眼での生活を目指すことができます。
- レーシック(LASIK):レーザーで角膜を削り、そのカーブを変えることで屈折力を調整する手術。
- ICL(眼内コンタクトレンズ):目の中に、虹彩と水晶体の間に小さなレンズを挿入する手術。角膜を削らないため、強度近視の方や角膜が薄い方にも適応できます。
これらの手術にはメリット・デメリットがあり、適応するかどうかは精密な検査が必要です。
まとめ:見え方の変化は、眼科に相談するサインです
近視・遠視・乱視は、私たちの生活の質(QOL)に直結する問題です。
【この記事のポイント】
- 屈折異常は、近視・遠視・乱視の3種類が代表的。
- 近視は遠くが、遠視は近くが特に疲れやすく、乱視は物がにじんで見える。
- 特に子供の遠視や乱視は、視力発達に影響する可能性があるため早期発見が重要。
- 矯正方法にはメガネ、コンタクト、オルソケラトロジー、手術など様々な選択肢がある。
- 自分に合った最適な方法を見つけるには、眼科での正確な検査と診断が不可欠。
「昔から目が悪いから」「もう年だから」と諦めないでください。見え方が変わった、目が疲れやすい、など、少しでも気になることがあれば、それは専門家への相談を促す体からのサインです。背景に他の病気が隠れている可能性もあります。
当院では、患者さん一人ひとりの目の状態はもちろん、ライフスタイルやご希望を丁寧にお伺いし、最適な見え方をご提案いたします。どうぞお気軽に、ご自身の「見え方」についてご相談ください。