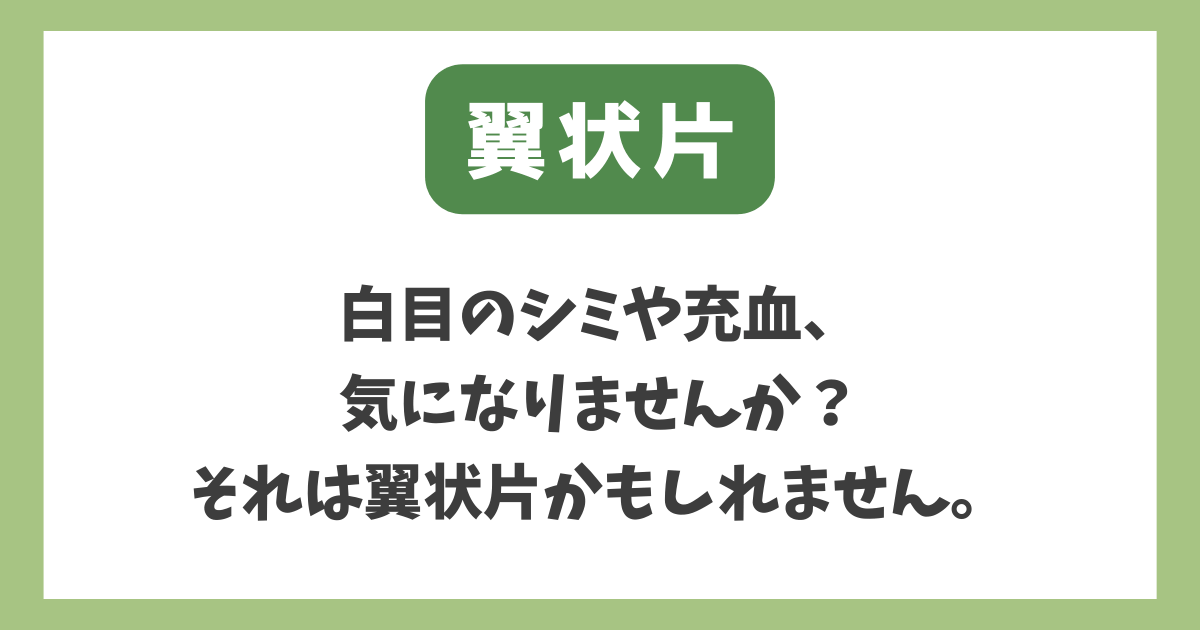「最近、白目から黒目に向かって、何か膜のようなものが伸びてきた」
「目がいつも充血していて、ゴロゴロする違和感がとれない」
「鏡を見ると、白目にできたシミがだんだん大きくなっている気がする」
このようなお悩みはございませんか? もし、白目(結膜)から黒目(角膜)に向かって、三角形の膜状の組織が侵入してきている場合、それは「翼状片」という目の病気である可能性が高いです。
翼状片は、その特徴的な見た目から「鳥の翼」のようであるため、この名前が付けられました。悪性の腫瘍ではなく、命に関わる病気ではありません。しかし、放置して進行すると、単なる見た目の問題だけでなく、強い乱視を引き起こして視力を低下させたり、最悪の場合、黒目の中心(瞳孔)にまで覆いかぶさり、失明につながる可能性もあるため、決して軽視はできません。
この記事では、眼科専門医の立場から、翼状片とは一体どのような病気なのか、なぜ発症するのか、そしてどのような治療法があるのかについて、詳しく、そして分かりやすく解説していきます。ご自身の目の状態を正しく理解し、適切な治療への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
翼状片とは? ~白目が黒目に侵入する病気~
翼状片は、眼球の表面を覆っている半透明の膜である「結膜(けつまく)」(いわゆる白目の部分)の組織が、異常に増殖して、隣接する「角膜(かくまく)」(黒目の部分)の上に侵入してくる病気です。多くの場合、目頭(鼻側)から発生し、ゆっくりと時間をかけて角膜の中心に向かって伸びていきます。
侵入してきた組織は、血管を伴った線維性の組織であり、充血して赤く見えたり、白っぽく濁って見えたりします。この組織自体は良性であり、目にできる「できもの」の一種ですが、問題はその「場所」と「進行性」にあります。
光を通す透明な窓であるべき角膜に、不透明な結膜組織が覆いかぶさることで、様々な視機能の障害を引き起こすのです。
「瞼裂斑」との違い
翼状片とよく似た病気に「瞼裂斑」があります。これは、白目の部分にできる、黄色っぽいシミや盛り上がりのことです。瞼裂斑は主に結膜の変性によって起こり、翼状片のように角膜の上に侵入してくることはありません。しかし、瞼裂斑に慢性的な炎症が加わることで、翼状片に移行していくケースもあるため、瞼裂斑の段階から紫外線対策などのケアを始めることが大切です。
翼状片の主な原因は「紫外線」
翼状片がなぜ発症するのか、そのメカニズムは完全には解明されていませんが、最も大きな原因は長年にわたる紫外線の暴露(紫外線ダメージの蓄積)であると考えられています。
長期間、無防備な状態で目に紫外線を浴び続けると、結膜の細胞がダメージを受け、異常な増殖(変性)を引き起こすきっかけとなります。特に、角膜はレンズのように光を集める性質があるため、目の鼻側の結膜に紫外線が集中しやすく、これが翼状片が目頭側から発生しやすい理由の一つとされています。
そのため、以下のような方は翼状片の発症リスクが高いと言えます。
- 屋外での仕事が多い方:農業、漁業、建設業、土木業など
- 屋外での趣味やスポーツを長年続けている方:サーフィン、釣り、ゴルフ、テニス、登山など
- 比較的、日差しの強い地域にお住まいの方
紫外線以外にも、以下のような要因が複合的に関与すると考えられています。
- 慢性の刺激:ホコリ、砂、潮風、化学物質などに常にさらされる環境
- 目の乾燥(ドライアイ):目の表面が乾いていると、外的刺激からのバリア機能が低下します。
- 加齢:多くは40代以降に発症し、年齢とともに有病率が上がります。これは、長年の紫外線ダメージが蓄積した結果と考えられます。
- 遺伝的要因:発症しやすい体質がある可能性も指摘されています。
翼状片は、あなたのこれまでの「人生で浴びてきた太陽光の量」が、目に現れたもの、と考えることもできるのです。
翼状片の症状 ~見た目だけの問題ではありません~
翼状片の症状は、その進行度によって様々です。初期の段階では、自覚症状がほとんどないことも少なくありません。
初期症状
- 美容的な問題:白目の一部が黒目にかかっているのが見た目でわかる。
- 充血:翼状片の部分には血管が多いため、目が疲れやすい、空気が乾燥している、寝不足などで容易に充血します。「いつも目が赤い」ことがお悩みで受診される方も多くいらっしゃいます。
- 異物感・違和感:目がゴロゴロする、しょぼしょぼするといった、ドライアイに似た症状を感じることがあります。
進行期の症状
翼状片がさらに進行し、角膜への侵入が大きくなると、視力に直接影響を及ぼす重大な症状が現れます。
- 乱視の発生・悪化:翼状片の組織が角膜を鼻側から引っ張ることで、角膜のきれいなカーブが歪んでしまい、強い乱視が発生します。ものが二重に見えたり、視界がぼやけたりするため、眼鏡をかけても視力が矯正しにくくなります。翼状片の手術を検討する最も大きな理由の一つが、この乱視による視力低下です。
- 著しい視力低下:翼状片が角膜の中心部、つまり瞳孔の領域まで達すると、光が目の中に入るのを直接妨げるため、視力が著しく低下します。この状態まで進行すると、手術で翼状片を切除しても、角膜に強い混濁が残り、視力が十分に回復しない可能性もあります。
- 眼球運動障害:非常に稀ですが、翼状片が大きくなり、結膜との癒着が強くなると、目の動きが妨げられることがあります。
このように、翼状片は見た目の問題だけでなく、放置することで視機能そのものを脅かす病気なのです。
翼状片の診断と治療方針の決定
翼状片の診断は、眼科医が目の状態を診察することで比較的容易につきます。当院では、主に以下の検査を行い、翼状片の進行度、視力への影響を正確に評価し、患者さん一人ひとりに最適な治療方針をご提案します。
- 視力検査:裸眼視力と矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを使った視力)を測定し、視力低下の有無を確認します。
- 細隙灯顕微鏡検査:眼科の診察で用いる顕微鏡で、翼状片の大きさ、厚み、血管の多さ(炎症の程度)、角膜への侵入度合いなどを詳細に観察します。
- 角膜形状解析:角膜のカーブの状態を精密に測定する検査です。翼状片によってどの程度の乱視が引き起こされているかを客観的に評価します。
翼状片の治療法 ~点眼治療と手術治療~
翼状片の治療法は、「薬物療法(点眼)」と「手術療法」の2つに大別されます。翼状片そのものを薬で治したり、小さくしたりすることはできないため、根本的な治療は手術となります。
1. 薬物療法(点眼治療)
翼状片がまだ小さく、視力に影響が出ていない初期の段階では、手術は行わずに経過観察となることが一般的です。
ただし、充血や異物感などの炎症症状が強い場合には、それらを和らげる目的で点眼薬を処方します。
- 抗炎症薬(ステロイドなど):翼状片の充血や炎症を抑えます。
- 人工涙液:目の乾燥を防ぎ、ゴロゴロとした異物感を軽減します。
重要:これらの点眼薬は、あくまで症状を緩和するための対症療法です。翼状片の進行を止めたり、治したりする効果はありません。定期的な検診で、翼状片の大きさや乱視の程度に変化がないかを確認していくことが非常に大切です。
2. 手術療法【根本治療】
翼状片を根本的に取り除く唯一の方法が手術です。当院では、以下のような場合に手術をお勧めしています。
- 視機能への影響:翼状片による乱視が強くなり、視力が低下してきた場合。
- 進行性:翼状片が明らかに角膜の中心に向かって大きくなってきている場合(瞳孔にかかる前の予防的な切除が望ましい)。
- 自覚症状:充血や異物感が強く、日常生活に支障をきたしている場合。
- 美容的な理由:見た目が気になり、切除を強く希望される場合。
- コンタクトレンズ装用困難:翼状片の盛り上がりが、コンタクトレンズの安定性を妨げる場合。
手術方法:再発を防ぐための「遊離結膜弁移植術」
翼状片の手術は、単に組織を切除するだけでは不十分です。単純に切除しただけだと、傷跡を修復しようとする力が過剰に働き、50%以上という高い確率で再発してしまうことが知られています。再発した翼状片は、もとよりも厚く、癒着も強くなるため、治療がさらに困難になります。
そこで当院では、この再発を最小限に抑えるための「遊離結膜弁移植術」を標準術式として推奨しています。これは、翼状片を切除した後の欠損部分に、患者さんご自身の正常な結膜(通常は上まぶたの裏に隠れている健康な部分)を採取し、移植(縫い付けまたは医療用接着剤で貼り付け)する方法です。
健康な結膜をバリアとして移植することで、血管や線維組織の再侵入を防ぎ、再発率を数%以下にまで劇的に低下させることができます。手術は点眼麻酔で行い、痛みはほとんどありません。手術時間も20~30分程度で、日帰りで行うことが可能です。
※当院では翼状片手術を行っておりませんので、必要な場合は提携病院へご紹介させていただきます。
手術後の経過
手術後は、一時的に目の充血やゴロゴロ感、涙が出るといった症状が現れますが、処方された点眼薬をきちんと使用することで、1~2週間で徐々に落ち着いていきます。術後しばらくは定期的な診察で、傷の治り具合や再発の兆候がないかを確認します。見た目が完全にきれいになるまでには、1~3か月程度かかります。
まとめ:白目の異常に気づいたら、まずは専門医にご相談を
翼状片について、ご理解いただけましたでしょうか。最後に、大切なポイントをまとめます。
- 翼状片は、白目が黒目に侵入してくる良性の病気です。
- 最大の原因は長年の紫外線ダメージです。屋外での活動が多い方は特に注意が必要です。
- 初期は無症状ですが、進行すると強い乱視を引き起こし、視力を低下させます。
- 点眼薬では治せず、根本治療は手術となります。
- 手術は、再発率の低い「遊離結膜弁移植術」が標準で、日帰りで行えます。
翼状片は、急激に悪化する病気ではありません。しかし、だからといって「まだ見えるから大丈夫」と自己判断で放置してしまうと、いざ手術が必要になったときには、視力回復が難しくなっている可能性もあります。大切なのは、専門医による正確な診断のもと、ご自身の翼状片が今どのような状態で、今後どうなる可能性があるのかを正しく把握することです。
大阪市鶴見区の大阪鶴見まつやま眼科では、翼状片の患者さん一人ひとりのお悩みやライフスタイルを丁寧にお伺いし、最適な治療のタイミングと方法を一緒に考えてまいります。白目のシミや充血、見え方の違和感など、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽に、そしてお早めにご相談ください。