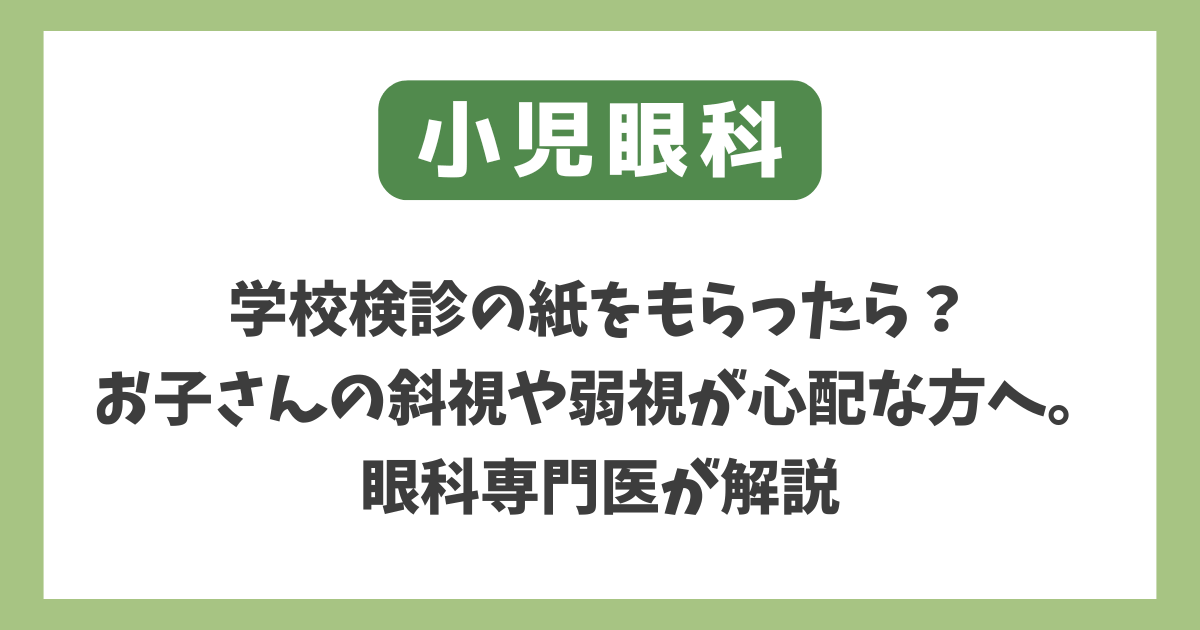「学校の視力検査で、判定結果の書かれた紙をもらってきた」
「うちの子、時々目の位置がずれている気がする」
「テレビを見るときに、顔を傾けたり、片目をつぶったりしている」
「色覚について、一度きちんと調べておきたい」
大切なお子さんの「目」について、このようなご心配や疑問をお持ちの保護者の方は、決して少なくありません。子供の視力は、生まれてから8歳頃までの間に急速に発達します。この非常に重要な時期に、何らかのトラブルがあると、視力の発達が止まってしまい、将来にわたって影響が残ってしまうことがあります。
しかし、多くの場合、お子さん本人は「見えにくい」ということを上手に訴えることができません。生まれた時からその見え方が当たり前だと思っているからです。だからこそ、周りの大人がいち早く変化に気づき、目の専門家である眼科医に相談することが何よりも大切になります。
この記事では、お子さんの目の健康に不安を感じている保護者の皆様に向けて、「小児眼科」で扱う代表的な4つのテーマについて、眼科専門医の立場から詳しく、そして分かりやすく解説していきます。
- 学校の視力検査で異常を指摘されたら
- 両目の視線が合わない「斜視」
- メガネをかけても視力が出ない「弱視」
- 色の見え方の特性を知る「色覚検査」
この記事を最後までお読みいただくことで、お子さんの目の発達の重要性をご理解いただき、適切な時期に必要な対応をとるための知識が身につきます。
なぜ「小児眼科」が重要なのか?
子供の目は、大人の目をただ小さくしたものではありません。日々成長し、変化している発達途中の器官です。特に、脳と目をつなぐ「視覚の神経回路」が発達する幼児期は、視力の発達にとって非常に感受性の高い「クリティカルピリオド」と呼ばれます。この時期にクリアな映像が網膜に映し出されていないと、神経回路の発達が妨げられ、将来メガネをかけても視力が1.0まで出ない「弱視」になってしまうのです。
小児眼科の最大の目的は、この大切な時期に、視力の発達を妨げる要因がないかをチェックし、もし問題があれば早期に治療を開始することで、お子さんが生涯にわたって良好な視機能を獲得できるようサポートすることにあります。
1. 学校の視力検査で異常を指摘されたら
学校から視力検査の結果の紙(受診勧奨のプリント)をもらってくると、ご心配になりますよね。まず、慌てる必要はありません。学校での検査は、静かで集中できる環境が整っているわけではないため、必ずしも正確な視力を反映しているとは限りません。しかし、それは「目の専門家による、精密な検査を受けてください」という大切なサインです。
眼科での精密検査
眼科では、お子さんの集中力にも配慮しながら、専門のスタッフが正確な視力検査を行います。さらに、ただ視力を測るだけでなく、目の病気がないかを診察します。特に重要なのが、調節麻痺薬(目薬)を使った屈折検査です。
子供の目は、ピントを合わせる力(調節力)が非常に強いため、本来は遠視があるのに、その力を過剰に使って無理やりピントを合わせ、「見かけ上の近視」になっていることがあります。調節麻痺薬を使うことで、この余分な緊張を完全に取り除き、その子が本当に持っている近視・遠視・乱視の度数を正確に測定することができるのです。
検査の結果、治療の必要がない場合もあれば、視力の発達を妨げている遠視や乱視が見つかり、メガネによる矯正が必要になることもあります。
2. 斜視|視線のずれが気になったら
斜視とは?
斜視とは、物を見ようとするときに、片方の目は目標物に向かっているのに、もう片方の目が違う方向を向いてしまっている状態です。目が内側に寄る「内斜視」、外側にずれる「外斜視」、上下にずれる「上下斜視」などがあります。
なぜ問題になるのか?
斜視は、見た目の問題だけでなく、視力の発達において2つの大きな問題を引き起こします。
- 両眼視機能が育たない:私たちは、左右の目で見た映像を、脳で一つに融合させることで、物を立体的に捉えています(両眼視)。しかし、斜視があると、左右の目に違う映像が映るため、脳が混乱し、この両眼視機能がうまく発達しません。
- 弱視の原因になる:脳は混乱を避けるため、ずれている方の目から送られてくる映像を無視(抑制)するようになります。その結果、使われなくなった方の目が「弱視」になってしまうことがあります。
斜視の治療
治療法は、斜視の種類や原因によって異なります。
- 眼鏡による治療:強い遠視が原因で起こる内斜視(調節性内斜視)の場合、遠視を矯正するメガネをかけるだけで、目の位置が正常になることがあります。
- プリズム眼鏡:光を曲げるプリズムレンズをメガネに組み込み、物の見える位置をずらすことで、両眼視を補助します。
- 手術による治療:目の向きをコントロールしている筋肉(外眼筋)の付着位置をずらして縫い直すことで、目の位置をまっすぐにする手術です。
3. 弱視|見逃されやすい「見えにくさ」
弱視とは?
弱視とは、メガネやコンタクトレンズで完全に矯正しても、良好な視力(1.0など)が得られない状態を指します。目の病気(先天性白内障など)が原因で起こることもありますが、多くは、視力の発達期に適切な視覚刺激を受けられなかったために、視力の発達が止まってしまった状態です。
弱視は、早期に発見し、感受性の高い時期(おおむね8歳頃まで)に治療を開始すれば、改善する可能性が非常に高いのが特徴です。そのため、3歳児健診や就学時健診が非常に重要になります。
弱視の主な原因
- 屈折異常弱視:両目ともに非常に強い遠視や乱視があるために、常にピントの合わないぼやけた映像しか見ておらず、視力の発達が止まってしまう状態。
- 不同視弱視:左右の目の度数に大きな差があるために、度の悪い方の目を使わなくなり、片目だけが弱視になってしまう状態。見た目には分かりにくく、片方の目がよく見えているため、発見が遅れやすいのが特徴です。
- 斜視弱視:前述の通り、斜視によってずれている方の目を使わなくなり、弱視になる状態。
弱視の治療
弱視治療の基本は、「脳に、弱視の目からの映像をきちんと見るように再教育する」ことです。
- 適切な眼鏡の装用:まずは、原因となっている屈折異常を、正確な度数のメガネで常に矯正し、網膜に鮮明な像を映してあげることが治療の第一歩です。
- 健眼遮蔽(アイパッチ治療):視力の良い方の目を、1日数時間アイパッチで隠し、弱視の目を強制的に使わせる訓練です。お子さんとご家族の協力が不可欠な、根気のいる治療です。
4. 色覚検査|色の見え方の特性を知る
色の見え方には、生まれつき個人差があります。多くの人とは少し違う色の見え方をするタイプを「色覚多様性(色覚異常)」と呼びます。これは病気ではなく、個性の一つです。日本人男性の約5%(20人に1人)、女性の約0.2%にみられる、決して珍しくない特性です。
治療によって治るものではありませんが、お子さん自身が自分の色の見え方の特性を知っておくことは、将来の学習や職業選択において、無用な混乱や不利益を避けるために非常に重要です。学校の授業で分かりにくい場面があったり、ご家族で色の認識が違うことに気づいたりした場合は、一度正確な検査を受けることをお勧めします。
眼科では、石原式色覚検査表やパネルD-15といった専用の検査器具を用いて、色覚のタイプと程度を正確に診断します。
まとめ:お子さんの目のことで心配があれば、いつでもご相談ください
子供の目の病気は、発見が遅れると、その後の人生に大きな影響を与えてしまう可能性があります。しかし、逆に言えば、大人が注意を払い、適切な時期に専門家に見せることで、守ってあげられる未来があるということです。
【この記事のポイント】
- 子供の視力は8歳頃までに発達するため、それまでの時期の目の管理が非常に重要。
- 学校検診の紙は、精密検査のサイン。必ず眼科を受診すること。
- 斜視や弱視は、早期に発見し、根気強く治療すれば改善する可能性が高い。
- 子供は見えにくさを訴えないことが多い。「おかしいな?」と思ったら、それが受診のタイミング。
当院では、お子さんが怖がらずに検査を受けられるよう、スタッフ一同、優しく丁寧な対応を心がけております。視能訓練士(ORT)という、子供の検査や訓練の専門家も在籍しております。お子さんの目のことで、少しでも気になること、不安なことがあれば、どんな些細なことでも構いません。どうぞお気軽に、当院の小児眼科へご相談ください。