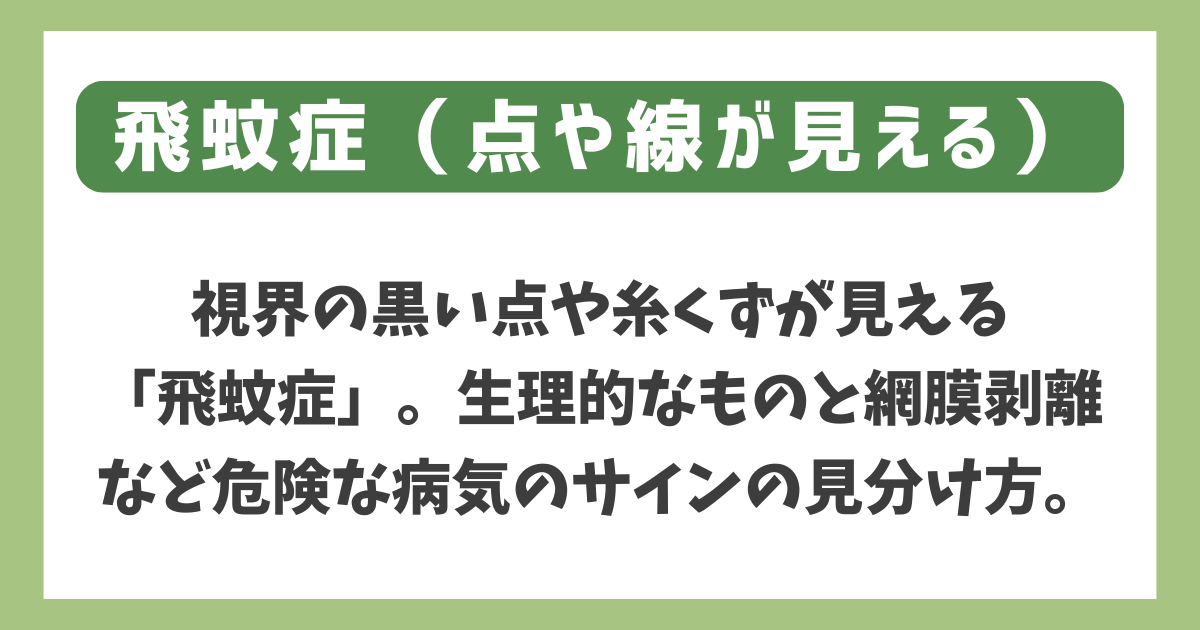「目の前に、黒い点や透明な糸くずのようなものが飛んで見える」
「視線を動かすと、フワフワと追いかけてくる」
「明るい場所や白い壁を見ると、特に気になる」
このような症状に心当たりはありませんか? それは「飛蚊症(ひぶんしょう)」と呼ばれる症状です。その名の通り、蚊が飛んでいるように見えることから名付けられました。
飛蚊症は、実は多くの人が経験するありふれた症状の一つです。そのため、「いつものことだから」「歳のせいだろう」と自己判断で放置してしまっている方も少なくありません。しかし、その飛蚊症、実は失明につながる重篤な目の病気のサインである可能性も隠れています。
この記事では、「飛蚊症」で検索されたあなたのために、その正体から原因、そして「心配ない飛蚊症」と「危険な飛蚊症」の見分け方、眼科での検査や治療の流れまで、専門的な観点から分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
ご自身の、そして大切なご家族の目の健康を守るため、まずはこの記事で飛蚊症に関する正しい知識を深めていきましょう。
飛蚊症の正体とは?―なぜ「点」や「線」が見えるのか
そもそも、目の前に見えている「点」や「線」は、本当にそこに存在しているわけではありません。その正体は、眼球の内部にある「硝子体(しょうしたい)」という組織の変化によって生じる「影」です。
私たちの眼球の大部分は、硝子体と呼ばれる、卵の白身のような無色透明のゼリー状の物質で満たされています。この硝子体は、99%が水分で、残りの1%はコラーゲン線維などで構成されており、眼球の形を保つ役割を担っています。
若い頃の硝子体は、均一で透明度が高いため、光はそのまま網膜(カメラでいうフィルムの部分)まできれいに届きます。しかし、何らかの原因でこの硝子体の中に濁りが生じると、その濁りが網膜に影として映り込み、私たちはそれを「黒い点」や「糸くず」として認識するのです。これが飛蚊症の基本的なメカニズムです。
では、なぜ硝子体に「濁り」が生じるのでしょうか。その原因は、大きく分けて2種類あります。
飛蚊症の主な原因 ―「心配ない飛蚊症」と「危険な飛蚊症」
飛蚊症の原因は、放置しても問題ない「生理的なもの」と、早期治療が必要な「病的なもの」に大別されます。この違いを理解することが、ご自身の目を守る上で非常に重要です。
1. 心配ない飛蚊症(生理的飛蚊症)
飛蚊症のほとんどは、この生理的な原因によるものです。主に加齢に伴う自然な変化であり、病気ではありません。
加齢による硝子体の変化(後部硝子体剥離)
最も多い原因が、加齢による硝子体の変化です。年齢を重ねると、ゼリー状だった硝子体は徐々にサラサラとした液体状の部分(液化)と、線維状の部分に分かれていきます。そして、硝子体全体が少しずつ縮んでいき、内側の壁である網膜から剥がれて隙間ができます。この現象を「後部硝子体剥離」と呼びます。
後部硝子体剥離は、多くの場合50代から60代で起こり始め、近視が強い方はより若いうちから起こる傾向があります。これは病気ではなく、誰にでも起こりうる老化現象の一つです。顔にシワが増えるのと同じような自然な変化と言えます。
この剥がれる過程で、硝子体のコラーゲン線維が凝縮して塊になったり、網膜との接着が強かった部分がリング状に剥がれたりします。この塊やリングが硝子体の中を漂い、網膜に影を落とすことで、急に「輪っかが見えるようになった」「黒いススのようなものが増えた」といった自覚症状につながります。
後部硝子体剥離自体は病気ではないため、これによって生じた飛蚊症は、基本的には治療の必要はありません。時間とともに濁りが視野の端の方へ移動したり、脳が慣れて気にならなくなったりすることがほとんどです。
生まれつきの飛蚊症
若い方でも飛蚊症を自覚することがあります。これは、お母さんのお腹の中にいた頃に、眼球が作られる過程で必要だった硝子体動脈という血管の名残が、生まれた後も硝子体の中にわずかに残ってしまうことが原因です。これも病的なものではないため、心配はいりません。
2. 危険な飛蚊症(病気が原因の飛蚊症)
ここからが特に注意していただきたい内容です。飛蚊症は、時に失明に直結するような重い目の病気の前触れとして現れることがあります。以下の病気は、緊急の治療を要する場合が多いため、症状の特徴をよく覚えておいてください。
網膜裂孔・網膜剥離
最も注意が必要で、緊急性が高い病気です。前述の「後部硝子体剥離」が起こる際に、硝子体と網膜の癒着が非常に強い部分があると、縮んでいく硝子体が網膜を強く引っ張ってしまい、その結果、網膜に穴(網膜裂孔)が開いてしまうことがあります。
網膜に穴が開くと、そこから液化した硝子体が網膜の下に入り込み、網膜を壁から剥がしてしまいます。これが「網膜剥離」です。網膜は、一度剥がれてしまうと栄養が届かなくなり、光を感じる細胞(視細胞)が徐々に死んでしまいます。治療が遅れると、たとえ手術で網膜を元の位置に戻せても、視力が回復しない、あるいは失明に至る可能性が高まります。
【危険なサイン】
- 飛蚊症の数が急激に増えた(墨を流したように見える、無数の点が見える)
- 稲妻のような光が見える、視界の端がピカピカ光る(光視症)
- 視野の一部がカーテンを引いたように見えない(視野欠損)
- 急激な視力低下
これらの症状が一つでも当てはまる場合は、網膜裂孔や網膜剥離を起こしている可能性が非常に高いです。様子を見ずに、すぐに眼科を受診してください。
硝子体出血
網膜の血管が何らかの原因で破れ、硝子体の中に出血が起こった状態です。出血した血液が硝子体の中に広がり、網膜に影を落とすため、飛蚊症として自覚されます。出血の量が多いと、霧がかかったように見えたり、急激に視力が低下したりします。
原因としては、糖尿病の合併症である「糖尿病網膜症」や、高血圧・動脈硬化が関わる「網膜静脈閉塞症」、加齢黄斑変性、外傷(目を強くぶつける)などが挙げられます。硝子体出血が起こっている場合、その背景にある原因疾患の治療が急務となります。
ぶどう膜炎
目の中に炎症を起こす病気の総称です。炎症によって、白血球などの炎症細胞が硝子体の中に染み出し、これが濁りとなって飛蚊症を引き起こします。
ぶどう膜炎の原因は、サルコイドーシスや原田病、ベーチェット病といった全身の免疫異常の病気や、細菌・ウイルス感染など多岐にわたります。飛蚊症の他に、「目がかすむ(霧視)」「充血」「目の痛み」「まぶしさ」といった症状を伴うことが多いのが特徴です。原因に応じた専門的な治療が必要となります。
放置は危険!すぐに眼科を受診すべき飛蚊症の症状チェックリスト
ご自身の飛蚊症が「心配ないもの」か「危険なもの」か、最終的には眼科で精密検査を受けなければ判断できません。しかし、以下のような症状がある場合は、緊急性が高い可能性があります。セルフチェックをしてみてください。
- 今まで見えていた浮遊物の数が、急に増えた
- 黒いススやインクのようなものが、たくさん見えるようになった
- 視界の端で、稲妻のような光が繰り返し走る(光視症)
- 視野の一部に、暗いカーテンや膜がかかったように見える部分がある
- 急に視力が落ちた、ものがゆがんで見える
- 目の痛みや充血、かすみを伴う
これらの症状に一つでも当てはまる方は、決して自己判断で放置せず、できるだけ早く眼科を受診してください。特に網膜剥離は時間との勝負です。早期に治療を開始できれば、良好な視力を維持できる可能性が高まります。
当院での検査と治療の流れ
「眼科に行ったら、どんなことをされるんだろう?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、飛蚊症を訴えて来院された患者さんに行う一般的な検査と、その後の治療の流れについてご説明します。
まずは、視力検査や眼圧検査といった基本的な検査を行い、どのような症状が、いつから、どのように見えるのか、詳しくお話を伺います。
飛蚊症の原因を調べる上で、最も重要な検査が「眼底検査」です。これは、眼球の奥にある網膜や視神経の状態を詳しく観察する検査です。
網膜の隅々までを詳細に観察するためには、目薬を使って瞳孔(ひとみ)を大きく広げる必要があります。これを「散瞳」と言います。散瞳薬を点眼してから瞳孔が十分に開くまで30~40分ほどかかります。
瞳孔が開いたら、医師が専用のレンズを通して、網膜に裂孔や剥離、出血、炎症などがないかを丁寧に確認します。この検査で、飛蚊症の原因が「生理的なもの」なのか「病的なもの」なのかを診断します。
検査結果に基づいて医師が診断をし、現在の目の状態と今後の治療方針について、患者さんに分かりやすくご説明します。
- 検査後、4~5時間は瞳孔が開いたままになります。
- 光がまぶしく感じたり、ピントが合わずぼやけて見えたりします。
- この状態での車やバイクの運転は危ないですので、避けてください。
- ご来院の際は、公共交通機関をご利用いただくか、ご家族などに送迎を依頼してください。
- まぶしさを軽減するため、サングラスや帽子があると便利です。
生理的飛蚊症と診断された場合
後部硝子体剥離など、病気ではない生理的な原因による飛蚊症と診断された場合は、基本的に治療の必要はありません。多くの場合、時間経過とともに慣れて気にならなくなります。ただし、後部硝子体剥離が進行する過程で、後から網膜裂孔が起こる可能性もゼロではありません。そのため、「症状に変化があった時(急に数が増える、光が見えるなど)は、すぐに再受診してください」とお伝えし、経過観察となります。
どうしても飛蚊症が気になって日常生活に支障が出るという方には、濁りをレーザーで破砕する治療や、硝子体を手術で取り除く治療(硝子体手術)といった選択肢もありますが、これらには合併症のリスクも伴います。治療のメリット・デメリットを十分に検討し、慎重に判断する必要があります。
病的飛蚊症と診断された場合
網膜裂孔や網膜剥離、硝子体出血などの病気が見つかった場合は、原因に応じた治療を速やかに行います。
- 網膜裂孔:網膜剥離への進行を防ぐため、穴の周りをレーザーで焼き固める「レーザー光凝固術」を行います。これは外来で可能な治療です。
- 網膜剥離:剥がれてしまった網膜を元の位置に戻すための手術(硝子体手術や強膜内陥術)が必要です。多くの場合、入院が必要となります。
- 硝子体出血やぶどう膜炎:原因となっている疾患(糖尿病網膜症、ぶどう膜炎など)に対する薬物治療(点眼、内服、注射など)が中心となります。出血が多い場合は、硝子体手術が必要になることもあります。
目のサインを見逃さないで―自己判断せず、まずは眼科へご相談を
ここまで読んでいただき、飛蚊症には様々な側面があることをご理解いただけたかと思います。
大切なのは、「たかが飛蚊症」と決して侮らないことです。あなたの目に見えているその「点」や「線」が、心配のない生理的なものなのか、それとも失明につながる危険な病気のサインなのか。それを正確に判断できるのは、眼科医だけです。
「最近、飛蚊症が気になるな」「数が少し増えた気がするけど、気のせいかな?」
そのように少しでも不安を感じたら、どうか自己判断で様子を見ずに、一度お近くの眼科を受診してください。検査の結果、もし「心配ない飛蚊症ですよ」と診断されれば、それだけで大きな安心材料になるはずです。そして、万が一病気が見つかったとしても、早期に発見できれば、それだけ治療の選択肢も広がり、良好な視機能を維持できる可能性が高まります。
特に、40代を過ぎたら、何も自覚症状がなくても年に一度は眼科検診を受けることをお勧めします。目の病気の多くは、初期段階では自覚症状がないまま進行します。定期的な検診は、あなたの「見える未来」を守るための、最も確実な方法です。
まとめ:飛蚊症はあなたの目からの大切なメッセージです
今回は、飛蚊症の原因から危険な症状の見分け方、眼科での検査・治療までを詳しく解説しました。
【この記事のポイント】
- 飛蚊症の正体は、目の中の「硝子体」の濁りが網膜に映った「影」である。
- 原因の多くは加齢による「生理的飛蚊症」で心配ないが、中には「病的飛蚊症」が隠れている。
- 「急に数が増える」「光が見える」「視野が欠ける」といった症状は、網膜剥離などの危険なサイン。すぐに眼科を受診する必要がある。
- 飛蚊症の原因を正確に知るためには、瞳孔を広げて行う「散瞳眼底検査」が不可欠。
- 自己判断は最も危険。少しでも気になったら、まずは眼科で検査を受けることが、あなたの目を守る第一歩。
飛蚊症は、あなたの目からの大切なメッセージかもしれません。そのメッセージを正しく受け取り、適切な行動をとることが、生涯にわたってクリアな視界を保つための鍵となります。私たちは、そんな皆さんの目の健康と安心をサポートするパートナーでありたいと考えています。どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
飛蚊症 よくあるご質問(Q&A)
「飛蚊症」について解説したメインページに続き、ここでは患者さんから特によく寄せられるご質問や、多くの方が検索されている疑問について、Q&A形式でさらに詳しくお答えしていきます。
ご自身の症状と照らし合わせながら、飛蚊症への理解を深めていきましょう。
- ストレスや疲れが原因で、飛蚊症になったり悪化したりしますか?
-
「最近仕事が忙しくて疲れているせいか、飛蚊症がひどくなった気がする」と感じる方は少なくありません。「ストレス」や「疲れ」と飛蚊症の関連性は、患者さんが非常に気にされるポイントの一つです。
結論から申し上げますと、ストレスや疲労が、飛蚊症の直接的な原因(硝子体内の濁りを物理的に作り出すこと)になるという医学的根拠は、現在のところ明確にはありません。飛蚊症の根本原因は、あくまで加齢などによる硝子体の物理的な変化です。
しかし、ストレスや過労によって自律神経のバランスが乱れると、普段は気にならないような些細な体の変化にも意識が向きやすくなります。そのため、以前からあった飛蚊症の症状を、より強く、あるいは不快に感じてしまう可能性は十分に考えられます。つまり「悪化した」のではなく、「気になりやすくなった」状態と言えるかもしれません。
ただし、「ストレスのせいだろう」と自己判断してしまうのは危険です。偶然にも、ストレスを感じていた時期に、網膜裂孔などの病的な変化が起きている可能性も否定できません。症状が強くなった、数が増えたと感じる場合は、心身のコンディションのせいだと決めつけず、原因をはっきりさせるためにも一度眼科で検査を受けることをお勧めします。
- 20代や30代でも飛蚊症になりますか?若い人の飛蚊症は大丈夫でしょうか?
-
飛蚊症は「加齢によるもの」というイメージが強いため、10代、20代、30代といった若い世代の方が症状を自覚すると、大きな不安を感じることがあるかと思います。
若い方でも飛蚊症になることは、決して珍しいことではありません。その原因として、主に2つの可能性が考えられます。一つは、胎児期に眼球が作られる過程で存在した血管の名残が、生まれつき硝子体内に残っている「生理的飛蚊症」です。これは病的なものではないため、心配はいりません。
もう一つ注意が必要なのが「強度の近視」です。近視が強い方は、眼球の奥行き(眼軸長)が通常より長くなっています。眼球が前後に引き伸ばされている状態のため、内部の硝子体にも変化が起こりやすく、加齢による硝子体の液化や後部硝子体剥離が、20代や30代といった若い年代から生じることがあります。さらに、網膜も引き伸ばされて薄くなっているため、網膜裂孔や網膜剥離を起こすリスクが、近視でない方に比べて高いことが知られています。
したがって、「若いから大丈夫」ということは決してありません。特に、強度の近視をお持ちの方で、急に飛蚊症の症状が現れたり、数が増えたりした場合は、年齢にかかわらず速やかに眼科を受診してください。
- 飛蚊症は、薬や目薬で治りますか?自然に消えることはありますか?
-
飛蚊症を自覚されている方が最も期待されるのが、「症状が消えてなくなること」だと思います。
残念ながら、現時点では生理的な飛蚊症の原因である硝子体内の濁りを、点眼薬や内服薬で直接的に溶かしたり、消したりする効果が証明された治療法はありません。硝子体の濁りは、コラーゲン線維などが凝縮した物理的な「塊」ですので、薬で分解することは非常に難しいのです。
では、一度発症したらずっとこのままなのかというと、そうとも限りません。「自然に治った」と感じるケースはあります。これは、硝子体の中を漂っている濁りが、時間とともに重力などで下の方へ移動したり、視野の中心から外れたりして、視界の邪魔にならない場所へ動くことがあるためです。また、最初は非常に気になっていた症状も、数ヶ月から数年経つうちに脳がその影の存在に「慣れて」、意識にのぼらなくなることも多くあります。これが「気にならなくなった=治った」と感じる主な理由です。
ただし、これはあくまで生理的な飛蚊症の場合です。網膜剥離など病気が原因の場合は、原因疾患を治療しない限り、症状は改善せず、むしろ悪化します。いずれにせよ、まずはその飛蚊症が治療の必要ないものか診断することが先決です。
- 飛蚊症の検査は、痛いですか?時間はどのくらいかかりますか?
-
眼科の受診をためらう理由の一つに、「検査が痛そう」「時間がかかりそう」といった不安があるかと思います。特に飛蚊症の検査について、流れをご説明します。
飛蚊症の原因を詳しく調べるためには、目の奥の網膜を隅々まで観察する「眼底検査」が必須です。この検査自体に痛みは全くありませんのでご安心ください。まず、散瞳薬という目薬を点眼し、瞳孔を大きく広げます。目薬がしみる感じが少しするかもしれませんが、痛みはありません。瞳孔が開くまでに30~40分ほどお待ちいただきます。
瞳孔が十分に開いたら、医師が「倒像鏡」や「細隙灯顕微鏡」といった専用の機器を使い、強い光を目に当てて眼底を観察します。少し眩しく感じますが、これも痛みはありません。診察自体は数分程度で終わります。この検査によって、網膜裂孔や剥離、出血の有無などを正確に診断できます。
検査全体としては、受付から会計まで1時間~1時間半程度みていただくとよいでしょう。ただし、検査後は散瞳薬の影響で4~5時間はピントが合わず、光をまぶしく感じます。この状態での車の運転は大変危険ですので、ご自身の運転でのご来院はお控えください。公共交通機関をご利用いただくか、ご家族の送迎でのご来院をお願いいたします。
- 飛蚊症を予防する方法や、これ以上増やさないためにできることはありますか?
-
まず、加齢に伴う生理的な飛蚊症を完全に予防する、という確実な方法は残念ながらありません。これは肌のシワや白髪といった老化現象と同様に、ある程度は避けられない自然な変化だからです。
しかし、目の健康を総合的に保ち、病的な飛蚊症のリスクを減らすために、日々の生活で心がけられることはいくつかあります。一つは、紫外線対策です。紫外線は眼球内の組織にダメージを与え、酸化ストレスを促進するため、白内障や黄斑変性などのリスク因子となります。屋外ではサングラスや帽子を活用しましょう。また、食生活も重要です。緑黄色野菜に多く含まれるルテインや、ブルーベリーなどに含まれるアントシアニンといった抗酸化物質を積極的に摂ることは、目の健康維持に役立つと考えられています。さらに、スマートフォンやPCの長時間使用は、目の疲れやドライアイの原因となります。適度に休憩を挟み、目を休ませることも大切です。
そして最も重要な「予防」は、危険な病気への移行を見逃さないための「定期的な眼科検診」です。年に一度は眼底検査を受け、目の状態をチェックすることが、失明につながる病気の早期発見・早期治療に繋がり、結果として視力を守る最善の策となります。
- 片方の目だけに飛蚊症の症状があります。両目ではないので大丈夫ですか?
-
「右目だけ」「左目だけ」というように、片方の目にだけ飛蚊症の症状が現れることは、非常によくあります。
飛蚊症の最も多い原因である「後部硝子体剥離」は、必ずしも左右同時に起こるわけではありません。多くの場合、片方の目にまず起こり、数か月から数年経ってから、もう片方の目にも起こります。そのため、症状が片目だけでも全く不思議なことではありません。
しかし、ここで注意が必要です。片目だけだから大丈夫、とは決して言えません。網膜裂孔や網膜剥離、硝子体出血といった緊急性の高い病気も、最初は片方の目にだけ急に発症することがほとんどです。例えば、「昨日までは何ともなかったのに、急に右目に無数の黒い点が見えるようになった」というような場合は、網膜裂孔やそこからの出血を強く疑います。
重要なのは、両目か片目かということよりも、「症状の現れ方」です。以前からある症状がずっと変わらないのであれば、生理的なものである可能性が高いですが、「急に出てきた」「急に数が増えた」「見え方が明らかに変わった」という場合は、片目だけでも危険なサインである可能性があります。症状がどちらか一方の目だけであっても、変化を感じた際には速やかに眼科を受診するようにしてください。